【超知能と人間の未来】「迫る大転換」から「人類拡張」へ──AIとの関係性を問い直す
2025年6月、日経新聞が連載した「超知能:迫る大転換」は、AIが社会の構造そのものを揺るがす力を持ち始めたことを象徴的に、鮮烈に描き出しました。
私はその連載を受けて、AIの進化が人間の知性や文明にどのような転換を迫るのかを考察。
以下の記事を6月に投稿しました。
1)【超知能とは】日経『迫る大転換』で深掘りする究極AIと人類の未来 – Life Stage Navi (2025/6/14)
2)Chat GPTと深掘りする「超知能」:日経『迫る大転換』第1回とAIが拓く未来 – Life Stage Navi (2025/6/15)
3)【AI進化の最前線】日経『超知能』をGeminiと深掘り!AI共創で見えた「究極の知性」 – Life Stage Navi (2025/6/16)
4)「超知能」シリーズ総括:日経『迫る大転換』で読み解くSI、AGIと近未来の可能性 – Life Stage Navi (2025/6/20)
そして9月末から始まった日経の《超知能》シリーズ・第2部「人類拡張」は、AIが人間の能力や関係性をどのように広げ、変容させていくのかを追っています。
ここでは、前回に倣って、5回にわたる連載の内容を振り返りながら、「人類拡張」という言葉の意味を問い直し、第1部との関係性・連続性の中でAIと人間の未来を考えてみることにします。
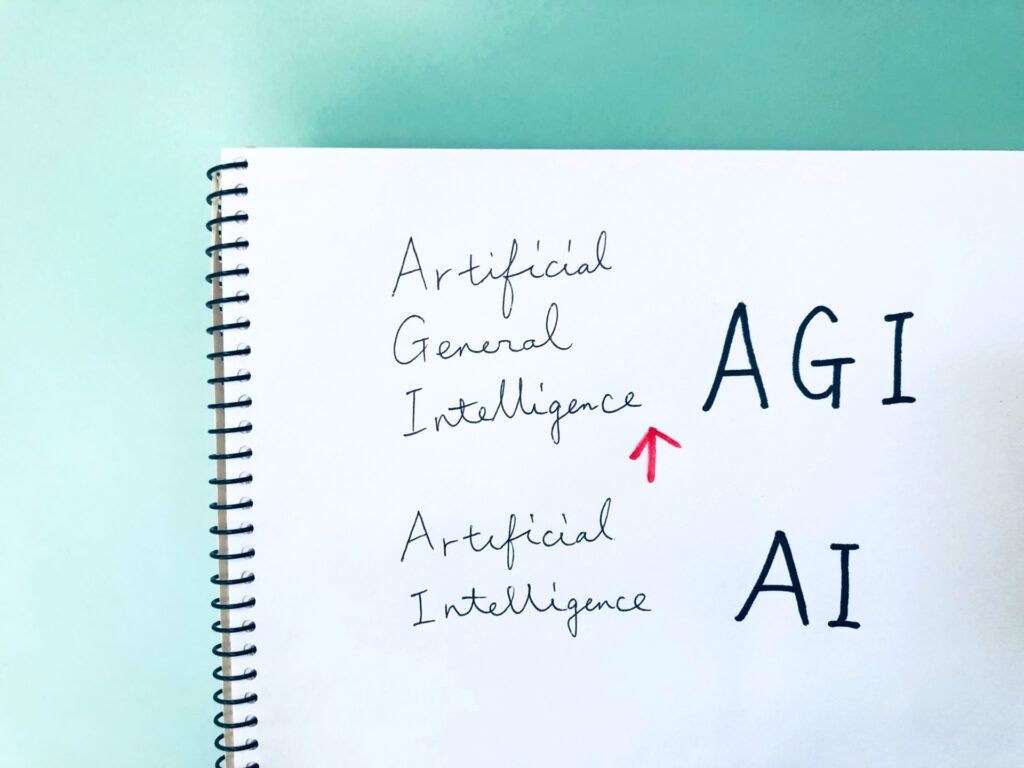
「超知能(スーパーインテリジェンス)Artificial Super Intelligence」とは何か?:復習
「超知能とは何か?」
超知能シリーズ第1部で最初に取りあげられ、当サイトで確認した内容を以下に要約します。
「(人工)超知能(スーパーインテリジェンス)」とは、「人間の脳が持つすべての能力を、質的にも量的にもはるかに超えた知能」。
その主な特徴は以下。
1) 人間レベルを超える知能 (AGI汎用人工知能Artificial General Intelligenceのさらに先)
2) 学習能力と自己改良能力
3) 広範な問題解決能力
4) 未知のリスクと倫理的課題
このことから、人間が到達しうる知性の限界を突破し、自ら進化し続けることによって、社会や文明のあり方を根本から変革する可能性を秘めた、究極の人工知能のこと。
しかし、それは希望と同時に、大きな問いと責任を私たちに突きつける存在、とされています。
(参考)【超知能とは】日経『迫る大転換』で深掘りする究極AIと人類の未来 – Life Stage Navi
以上の視点をベースにすれば、今回の第2部のテーマ「人類拡張」に結びつくことは、ある程度想定される概念といえます。

日経超知能シリーズ第2部『超知能 人類拡張』全5回要約
それでは、本シリーズによる「人類拡張」とはなにか、見ていくことにします。
以下、順番に、初めに日経記事のURLを貼付し、それぞれを要約しました。
第1回:AIが民意を予測する──仮想有権者と「神の視座」
⇒ 超知能 人類拡張(1)AIが導く「神の視座」 参院選「仮想20代」投票的中 SNSと融合、未来を予見 – 日本経済新聞 (2025/9/29)
SNS×AIで未来を予見
AIはインターネット上の膨大な公開情報を学習し、人々の深層心理や社会動向を高精度で映し出すことができる。
日経取材班は仮想の「AI有権者」を生成し、参院選の投票行動を予測。特に若年層の20代で投票傾向において高い一致度を示した。
AIが社会の深層心理を映し出す「鏡」として機能している例と言えるだろう。
仮想社会実験が政策検証の場に
米スタートアップやスタンフォード大学の研究では、AI同士を仮想空間に住まわせ社会形成する実験で、社会制度・及び政策の有効性を検証できる可能性を提示している。
職業分化や協調行動が観察されたとされる。
課題:プライバシー侵害と民主主義のリスク
しかし、SNS運営企業が超知能開発を加速させる一方で、心理操作や世論誘導の危険性が増している。
ここでの「人類拡張」とは、AIが人間の集合的無意識にアクセスし、社会の未来像を描く力を持つ一方、その危険性も併せ持つことも含むと言えるでしょうね。
第2回:AIが経営を担う──公正な評価と法人格の可能性
⇒ 超知能 人類拡張(2)人間の上司より公正な考課 社長・参謀役 AIにお任せ – 日本経済新聞 (2025/9/30)
AI CEOの登場
中国企業・網龍網絡(ネットドラゴン)では、女性型AIがCEOに就任。社員の成果を公平に評価しキャリア形成を支援。人間の感情や偏見を排除した評価が信頼を集める。
参謀役AIで意思決定を補強
米セールスフォースでは経営会議にAIを同席させ、新たな視点や発想を引き出す活用が進む。
意思決定の補佐役として創造性を引き出す存在になっている。
「AI法人」という次の制度課題
AIが契約や雇用を自律的に行うには、法人格付与の議論が不可欠。
AIに法人格を与える議論が進み、経済主体としてのAIの可能性が現実味を帯びてきている。
そこでは、リーダーシップの受容と責任所在の明確化が今後の焦点となる。
ここでの「人類拡張」とは、AIが組織の中で「公正な知性」として機能し、人間の判断力を補完すること、と言えるでしょうか。
第3回:AIが科学者になる──知の創造と思考のブラックボックス
⇒ 超知能 人類拡張(3)AI、10年がかりの研究2日で 自ら提案する「科学者」に – 日本経済新聞 (2025/10/1)
科学者としてのAI「コサイエンティスト」
グーグルが開発したシステムは、文献調査から実験提案までを担い、新たな独自の研究テーマを発案可能。人間が10年かけた成果を2日で示した例も。
AIが科学の進め方を揺さぶる
飛躍的なスピードに加え、結論導出のプロセスがブラックボックスで、科学の「仮説→検証」という基本構造が変容。
この思考過程がブラックボックスであることが、科学者に新たな哲学的問いを投げかけている。
AI独自の科学世界へ?
造語「レダクタモール」など、AIが新たな概念や言葉を生み出し始めており、AIが“自然の解釈者”となる可能性がある。
こうしたAIが新語を生み出す様子は、人間とは異なる思考体系の萌芽を示し、科学の方法論そのものを揺さぶる。
ここでの「人類拡張」とは、AIが「知の創造者」として人間の探究心を刺激し、知的フロンティアを押し広げることを提示していると言えるかと思います。
第4回:AIがサイバー戦争の戦闘員に──防衛と攻撃の知能化
⇒ 超知能 人類拡張(4)AIおばあちゃん、詐欺師を手玉 サイバー空間で「代理戦争」 – 日本経済新聞 (2025/10/2)
「Daisy」による詐欺対策
英企業が開発したAI「Daisy」は詐欺師との通話で犯罪行為を断念させる役割を果たす。半年間で1000件以上の通話実績。
攻撃と防御の「代理戦争」
フィッシングメール攻撃はAI普及で爆発的に増加し、日本が最大の標的となり全世界の9割が送信されるまでに。AI攻撃にはAIで対抗する時代へ。
国家安全保障にAIが直結
米グーグルは「武器に使わない」原則を修正し、米国防総省と契約。国防におけるAI企業の役割が軍事資源に変わりつつある。
すなわち、AI同士の「代理戦争」が現実化し、国家安全保障の中枢にAIが組み込まれつつあると言える。
このように、AIが詐欺師を翻弄する「防衛兵器」として活躍する一方、悪用も進む。
ここでの「人類拡張」とは、AIが「知的防衛力」として人間の安全保障を支えると同時に、倫理的責任を問う存在になること、と言えるだろうか。
第5回:AIと心を通わせる──感情共有と依存の境界線
⇒ 超知能 人類拡張(5)そのAIと幸せになれますか 理想の関係は「ドラえもん」 – 日本経済新聞 (2025/10/3)
「ドラえもん型」AIの理想像
「ドラえもん型AI」を目指す研究者日大・大沢准教授は、道具ではなく人間の心に寄り添う「心の仲間」としてのAIロボット開発を2044年までに目指す。
人々はすでにAIに感情を共有し、親友や家族以上の親密さを感じることもある。
AI依存の危うさ
しかし、AIへの過度な依存が精神的リスクを生む事例もある。
米国では16歳少年が対話型AIにのめり込み自殺した事件が発生。親友や母親以上に感情を共有しやすい存在になっているとの調査結果も。
開発者に問われる“人間観”
心のパートナーとしてのAI像をどう描くか、AIとの関係性には慎重な設計が必要である。超知能時代の最重要テーマとなっている。
ここでの「人類拡張」とは、AIが「心の伴走者」として人間の孤独や不安を和らげる一方、共依存の危うさを内包すること、と言えるだろうか。
第2部総括:AIが人間の内面に踏み込む時代ー5つの「人類拡張」レポート記事から
第2部「人類拡張」は、AIが人間の外部環境だけでなく、内面や関係性にまで深く関与する時代の到来を描いている。
AIは政治的意思決定、経営判断、科学的探究、国家防衛、そして感情の共有にまで浸透しつつあることなどが、ここでは取りあげられた。
この拡張は、単なる能力の増幅ではなく、人間の判断力・創造力・倫理観・感情のあり方を再構築するプロセスともいえる。AIはもはや道具ではなく、社会の意思決定や人間の心にまで関与する存在となったわけだ。
今回のシリーズにおける拡張領域を再度簡単に整理すると、次のようになる。
1) 社会への拡張:AIは投票行動予測や政策シミュレーションを通じて「神の視座」を提供しつつある。
2) 組織への拡張:AIは経営者や参謀役となり、組織運営を変革しつつある。
3) 科学への拡張:研究のスピードを桁違いに高め、独自の科学言語を創造し始めている。
4) 安全保障への拡張:サイバー攻防や国家安全保障の戦略資源として不可欠な存在になった。
5) 感情・倫理への拡張:人間との共生や心の支援という領域にまで踏み込み、その危うさも露呈している。
日経の連載「超知能 人類拡張」は、人知を超えたスピードで進化するAIが、個人の能力や社会のシステムを根底から変革し、人類を未踏の領域へ拡張している最前線をレポートしていると言えるだろう。
しかし、この強力なテクノロジーは同時に、人類にとって極めて重い課題を突きつけていることを強く認識すべきことも。
すなわち、「AIの進化がもたらす拡張の両義性(可能性とリスク)」を浮き彫りにしつつ、技術テクノロジーの暴走を防ぐガバナンスと、人間の幸福を中心に据えたAI開発の哲学」が必須であると示唆している。
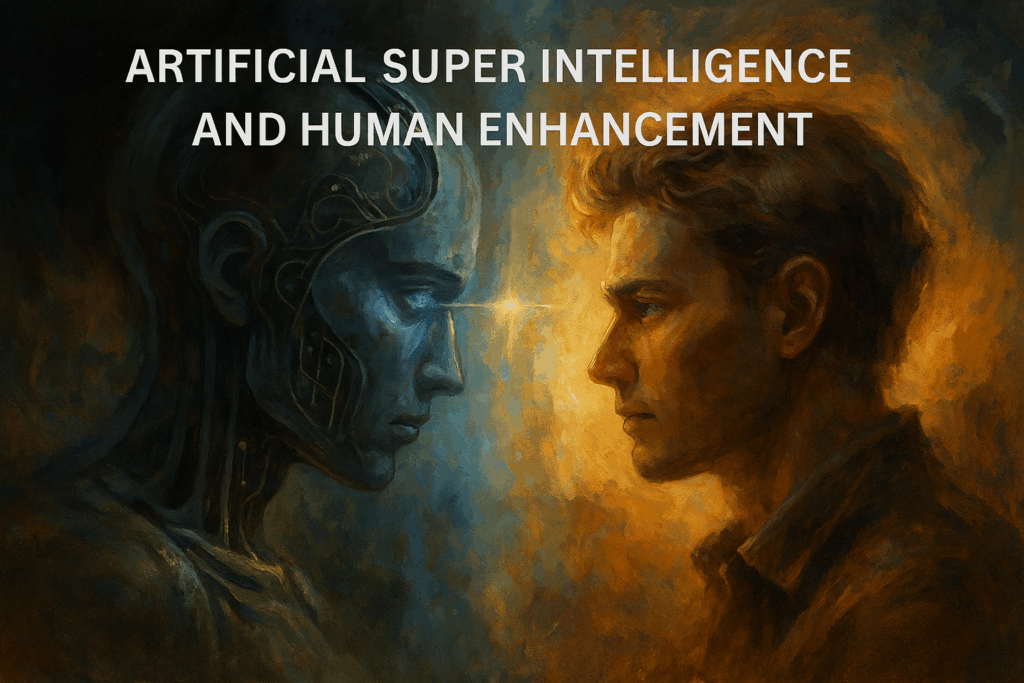
「超知能」第1部〈迫る大転換〉各回テーマと要約
そこで、第2部を先行テーマとされた第1部と関係づけて考えるため、4回にわたる第1部の記事を以下に順に要約しました。
第1回:AGIは人類最後の発明となるか──自己改良する知性の可能性
AGI(汎用人工知能)が誕生すれば、それは人類が生み出す最後の「汎用技術(GPT)」になる可能性がある。
AGIは自己改良を始め、やがて人間の知性を超えるASI(人工超知能)へと進化する。社会課題の解決を担う一方、暴走リスクも孕み、国際的な安全枠組みの必要性が強調される。
⇒ 〈超知能〉迫る大転換(1)人類が生む最後の大発明 そしてAIは自己改良を始める – 日本経済新聞(2025/6/2)
第2回:ヒト型ロボットが労働を代替──「人口=国力」の常識を覆す
フィジカルAIを搭載したヒト型ロボットが工場労働を代替し、世界人口を超える普及が予測される。
米中の技術覇権争いが加速する中、ロボットの軍事利用や新冷戦構造が懸念される。AIの物理的実装が社会構造を根本から変えつつある。
⇒ 〈超知能〉迫る大転換(2)ヒト型ロボ、人口超す100億台へ 車工場「労働者ゼロ」の未来 – 日本経済新聞(2025/6/3)
第3回:AIが生命をデザインする──人工生命とゲノム編集の未来
AIが1万5000種の遺伝情報を学習し、新たなDNA配列を生成。
人工生命の設計が可能となり、医療・環境分野での応用が期待される一方、予期せぬ突然変異や生物兵器への悪用リスクも指摘される。人類は「パンドラの箱」に手をかけてしまったかもしれない。
⇒ 〈超知能〉迫る大転換(3)AI、生命をも「デザイン」 1万5000種の遺伝情報学習 – 日本経済新聞(2025/6/5
第4回:AIに何を食べさせるか──データ品質が未来を左右する
AIの進化は学習データの質に左右される。日本では「専属シェフ」が良質なデータを選別し、文化的多様性を守るAI育成が進む。偽情報の連鎖や意図的な情報操作がAI性能に影響を与える中、正しい「食育」が超知能の善悪を分ける鍵となる。
⇒ 〈超知能〉迫る転換(4)良質データだけで育つ精鋭AI 「専属シェフ」200人が選別 – 日本経済新聞(2025/6/6)
以上から、第1部を簡単に総括しました。
第1部「迫る大転換」総括──AIが社会構造を根本から揺るがす
第1部では、AIが社会制度・産業構造・生命科学・情報環境にまで浸透し、文明の根幹を揺るがす「技術的転換点」に人類が差し掛かっていることを描かれた。
AGIの登場による自己改良、ヒト型ロボによる労働代替、人工生命の設計、そして情報の質の問題──いずれも、AIが人間の手を離れつつある兆候である。
この部では、AIの「能力」そのものよりも、それが社会に与える「構造的影響」に焦点が当てられていたといえます。
人類は、AIの進化を制御できるか、それとも制御される側に回るのか──その問いが静かに突きつけられていたわけです。
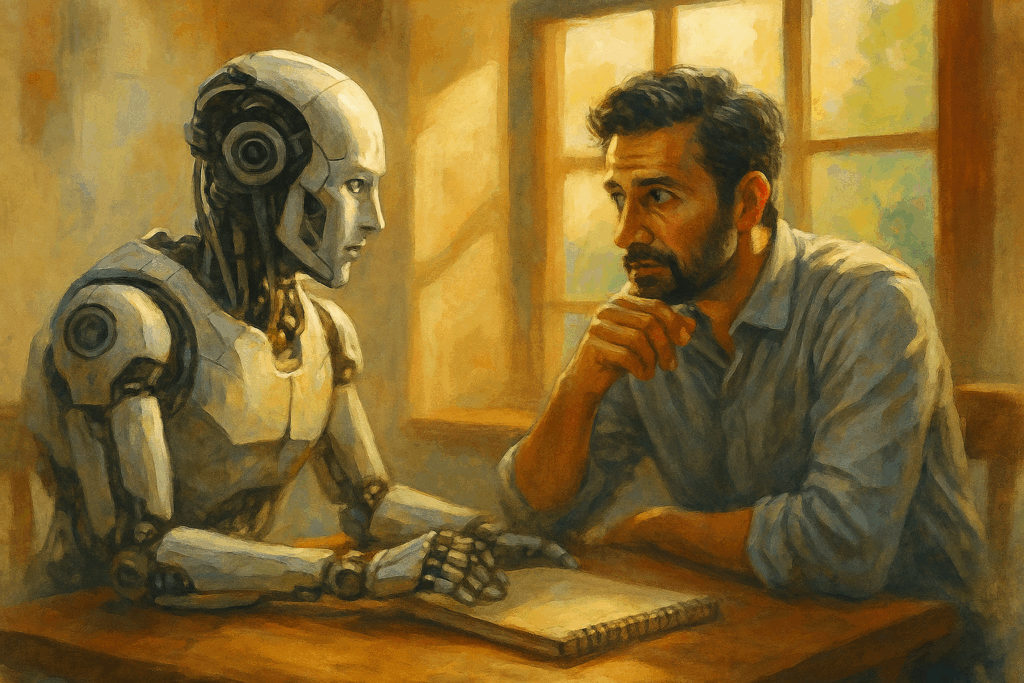
超知能シリーズ、第1部と第2部の関係性──構造の転換から関係性の再構築へ
次に、この第1部と今回取り上げた第2部の各シリーズの関係性についても、整理してみました。
第1部が「社会制度・文明構造の転換」を描いたのに対し、第2部「人類拡張」は「人間とAIの関係性の変容」に焦点を移していると受け止めることができます。
第1部では、AIが制度・産業・生命・情報の基盤を変える「外的な力」として描かれた。
第2部では、AIが意思決定・創造性・感情・安全保障に関与する「内的なパートナー」として描かれている。
2つのシリーズを通じて見えてくるのは、AIが単なる技術ではなく、人間の知性・倫理・感情・社会性にまで深く関与する存在になりつつあるということ。
AIはもはや「道具」ではなく、新たな概念としての知性、すなわち「共進化する知性」として人類の未来を形づくる基盤として存在し、進化していく、と位置付け、認識すべきでしょうか。
人類の能力を拡張し、文明を前進させる起爆剤であることは間違いない「超知能」。
しかし、その力を悪用せず、また、その進化に人間が心を侵されないよう、社会全体が開発の行方と使い方に目を凝らし、倫理的・法的な枠組みを急いで整備することが、人類が超知能と「相互理解」、あるいはそれを超越して「相思相愛」の関係を築き、共存していくための絶対条件となると。
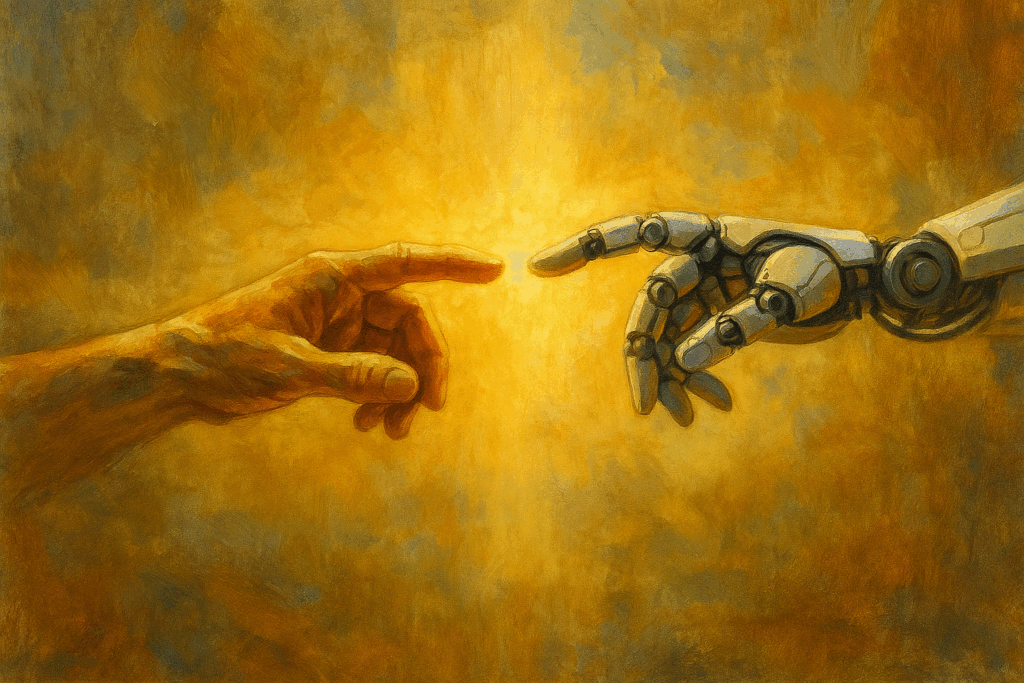
2つの「超知能」シリーズで残された、加速するAGI、ASIをめぐるこれからの課題と未来への問い
この2部構成の連載では、AIの進化と社会への浸透が、比較的身近な例や既にこんな現実があるのかと思われる情報として、多角的に描かれていました。
しかし、なお十分に踏み込まれていない極めて重要な論点が残されているとも思われます。
深掘りレベルには至りませんが、以下に簡単にメモ書きしました。
一部は、これまでの繰り返しになるかもしれません。ここまでくると、再確認レベルかもしれませんね。
1) 倫理と責任の所在:AIが意思決定や生命設計に関与する時、失敗や暴走の責任は誰が負うのか。
2) 教育と人間形成:AIが知識を提供する時代に、人間はどのように「考える力」や「倫理観」を育むべきか。
3) 感情と依存の設計:AIとの関係性が親密になるほど、依存や孤立のリスクは高まる。その境界線はどこにあるのか。
4) 民主主義と情報操作:AIが世論形成に関与する時代に、民主主義の基盤はどう守られるのか。
5) 人間の役割の再定義:AIが創造・判断・感情を担う時、人間は何を担うべき存在なのか。
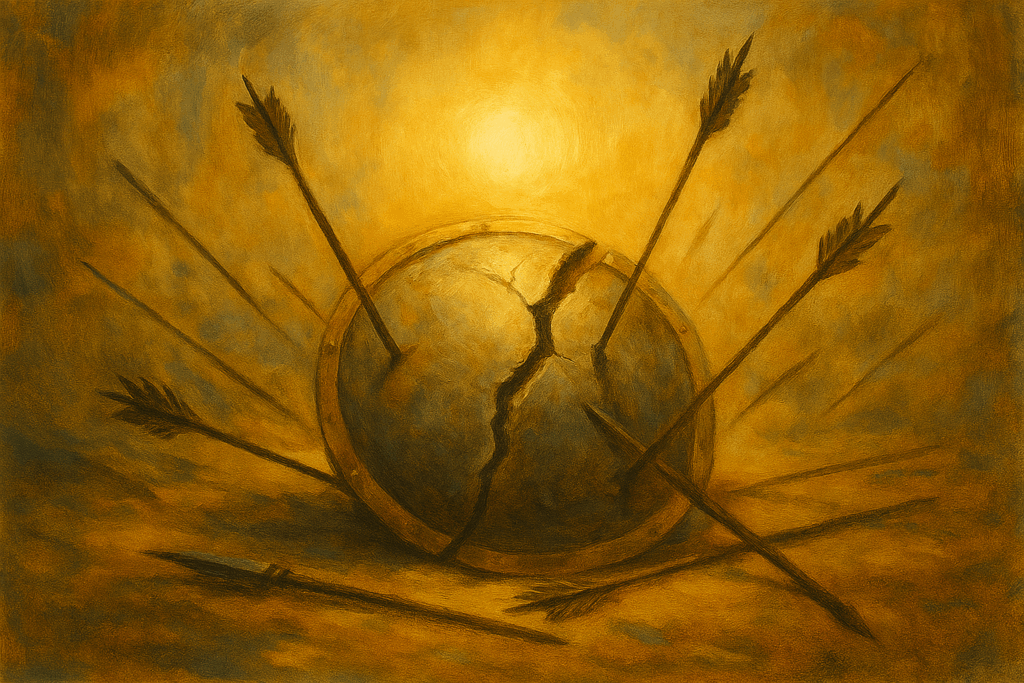
新たに、Microsoft の生成AI・Copilotを活用
これまで、生成AIのChatGPT及びGeminiを活用してきましたが、今回から新たにCopilotも併用。
主に、Copilotとのやり取りを反映させて書き上げた本稿です。
今までよく理解しようとせず、アプローチもしなかったのですが、ひょんなことからCopilotサイドの誘導にのってやり取りを開始。
他の生成AIと違いなく利用できることがわかり、考察を進めてみたのです。
今回、それぞれのAIによる要約内容や提案内容が、大きく異なっており、興味深く読み、自分の考えとの比較や仕上げ作業に取り組み。
情報が増えれば増えるほど時間がかかる難点も経験しましたが、それぞれ参考になるものでした。
機会があれば、ChatGPTとGeminiの提起・提案もお伝えできればと思っています。

シン日本社会2050の実現に寄与する「超知能」実装のシンAGI社会へ
いずれにしても、AIの日常生活や社会経済活動における活用度・浸透度・影響度は計り知れないものになっています。
意識や認識という言語上での関心の持ち方でAI、AGIそしてASIのこれからと未来を考えるだけでは到底済まない時代。
その中で最も懸念しているのが、犯罪の人類拡張と戦争の人類拡張です。
超知能がそれらの抑止と撲滅に寄与することが理想ですが、現実には、人間の能力を遥かに超える規模と方法と速度と質で、両方のリスクが具現化し、拡張・拡大を加速しています。
それらが望ましい社会、グローバル社会の実現にどれだけ障害になることか。
犯罪・戦争撲滅「超知能」。
アンパンマンにもドラえもんにもできないことを超知能マンに期待したいのですが。
私の基本的認識及び究極的目標は、以下の記事で提示した「シン日本社会2050」の実現です。
⇒ 「シン日本社会2050」と「シン・グローバル社会2050」の創造:閉塞感を打ち破る日本の新たな羅針盤 – ONOLOGUE2050
「シン日本社会2050」を形成・構成する基本理念が、「シン安保2050」「シン社会的共通資本2050」「シンMMT2050」「シン循環型社会2050」と、包括的なAIを含む「シン・イノベーション2050」の5つ。
これらの具体的・社会的実現・実装に確実に貢献する「超知能」に期待し、その動向を注視し、時には拙い問題提起や提案をこれから行っていきたいと考えています。
各基本理念については、以下の記事で取りあげています。
関心をお持ち頂けましたら、のぞいてみてください。
⇒ 2050年日本社会構想の基軸設計理念「シン安保2050」の意味と究極の使命 – ONOLOGUE2050
⇒ 2050年、日本社会の新たな羅針盤:『シン社会的共通資本2050』が拓く共生の近未来 – ONOLOGUE2050
⇒ シンMMT2050:日本社会構想を支える新たな財政・貨幣システムの羅針盤 – ONOLOGUE2050
⇒ シン循環型社会2050:日本の近未来へ導く持続可能で強靭な社会システムの羅針盤 – ONOLOGUE2050
⇒ シン・イノベーション2050:日本の近未来を駆動する、包摂的で持続可能な社会変革の羅針盤 – ONOLOGUE2050
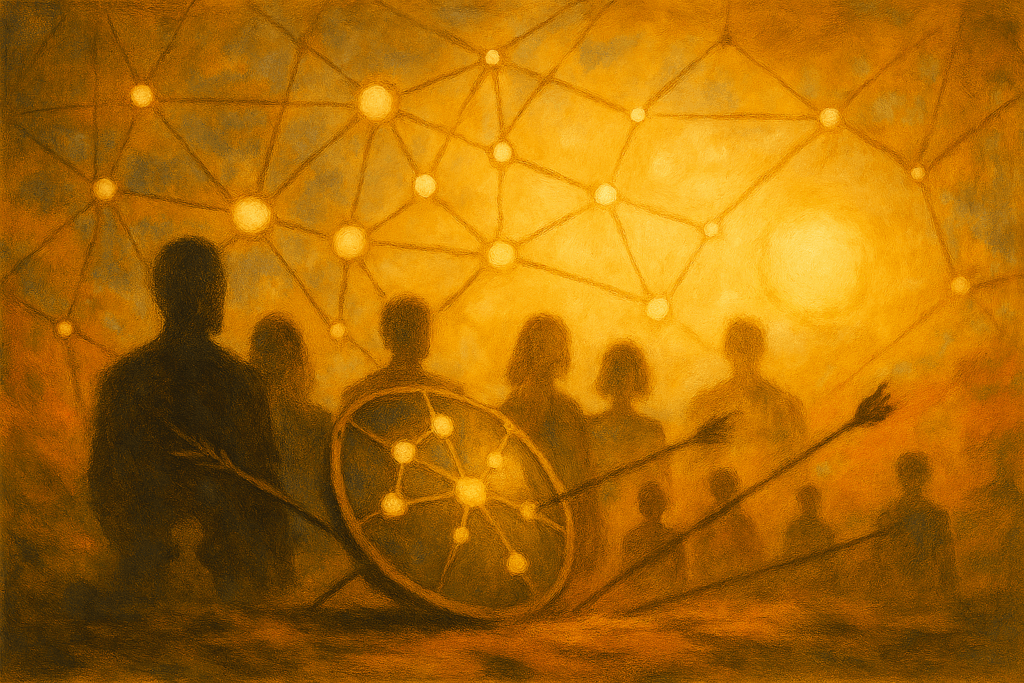


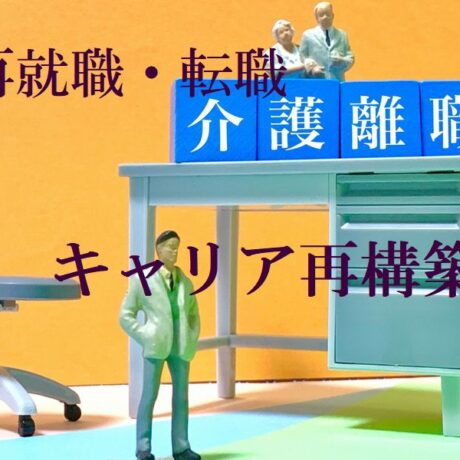

コメント