AIの進化は、もはや一部の専門家や企業の話ではなく、私たち一人ひとりの働き方や暮らし方に直接影響を及ぼす段階に入っています。
これからの日本社会では、労働市場そのものが大きく姿を変えていくでしょう。
今、米国では、AIによるホワイトカラーの代替が進み、大卒の若年層でもキャリアの不安定化が始まっています。
この「対岸の火事ではない」異変を教訓として、私たちはどう備えるべきでしょうか。
本稿は、「シンAI社会時代における個人のキャリアをいかに創造するか」という問いに対し、まず現状の課題を整理(1章・2章)し、その上で、個人が主体的に取り組むべきセルフラーニングの考え方(3章)や、AI時代を生き抜くための具体的かつ多角的な「生き方・働き方の備え」(4章)を考えることにします。
――「人間らしく働く」ことを、もう一度考え直すとき
1.加速するAI社会化で急速に変わる米国の若い世代の労働市場・雇用状況
2025年10月26日付日経で以下の記事が掲載されました。
⇒ AI猛進の米国、若者の働き口に異変 学位あっても就職難→ブルーカラー選ぶ 覇権狙い開発優先の現実 – 日本経済新聞
同記事を導入部分として、これからのAI社会における働き方・労働と雇用市場について考えてみたいと思います。
このテーマで、日経記事を要約し、そこから考えうる事項を補足することにします。
日経、AI猛進米国での若者の労働市場激変レポート要約
1)AIによるホワイトカラー職の代替と若者の就職難
・大卒の雇用状況の悪化:
米国の失業率は全体では安定(4%台前半)しているにもかかわらず、20~24歳の若年層に限ると、2024年12月の7.5%から25年8月には**9.2%**まで失業率が上昇しました。
・影響を受ける層の変化:
従来は景気減速局面で影響を受けやすい高卒などの比較的学歴の低い層が苦労しましたが、今回は景気変動の影響を受けにくいとされてきた大卒に苦労が集中している点に特徴があります。
・AIによる職務代替:
スタンフォード大学の試算では、ソフトウエア開発の分野で22~25歳の雇用が2022年後半のピーク時から25年7月までに約20%減。コード生成などの体系化された知識がAIに代替されやすいことが背景です。
顧客対応のカスタマーサービスでもAIの活用が進んでいます。
セントルイス連銀のエコノミストらも「AIによる雇用喪失の初期段階を目撃している可能性がある」と関連を認めています。
・経営層の見解:
フォード・モーターのジム・ファーリーCEOは、「AIによってホワイトカラー職の雇用が半減する」と予想しています。
2)学位信仰の崩壊とブルーカラーへのシフト
・大学教育の価値への懸念:
10~20代のZ世代の親を対象とした調査では、「大学の学位があれば長期的な雇用安定が保証される」と答えた割合はわずか16%にとどまりました。
・「自動化されにくい仕事」への需要: 親の77%が「自動化されにくい仕事」を選ぶことが重要と指摘しています。
・職業訓練校へのシフト:
配管工や大工などの技術を習得する職業訓練校の入学者数が2025年春に前年比12%増となり、大学入学者の伸び(4%増)を大きく上回っています。
フォードCEOも、熟練工確保の重要性を訴え、若者の職業訓練校へのシフトを歓迎しています。
以上の要約から想起できることを補足的に考えてみました。
AI社会化がもたらす「ひずみ」と若者のキャリア観の変容
1)📈 AI経済の成長の裏側にある「雇用の恩恵の偏り」
AI技術の急速な進化と導入は米国経済に高成長をもたらしていますが、その恩恵は均等には分配されていません。
特に、雇用市場において顕著な「ひずみ」が生じています。
・投資の偏重(クラウディングアウト):
AIを支えるデータセンター建設への空前の投資は、建設業や発電業といった特定分野に集中しています。
これにより、製造業や都市インフラなど他の重要産業への投資や労働力供給が後回しになる「クラウディングアウト」の懸念が高まっています。
実際、製造業では2033年までに190万人もの労働力不足が予測されており、これは経済的・国家安全保障上の問題となり得ます。
・雇用の不均衡:
AIが知的・定型的なホワイトカラー職を代替する一方で、AI時代に不可欠なインフラ整備(データセンター関連)の現場作業や、熟練を要するブルーカラー職(配管工、大工など)の需要が急増し、雇用における恩恵の偏りが明確になっています。
2)🎓 「学歴=安定」神話の崩壊とキャリア観の逆転
AIによる知的労働の代替は、特に若い世代のキャリア観と、これまで社会の前提とされてきた「学歴信仰」に根本的な変化をもたらしています。
・若者の「代替されにくい職」志向
大卒の学位が長期的な雇用安定を保証するという信頼が揺らぎ、多くの若者やその親が「AIに代替されにくい職」を選択するようになっています。
これは単なる一時的なトレンドではなく、教育制度やキャリア形成の前提そのものが揺らいでいることを意味します。
・「知的労働のブルーカラー化」の示唆
AIが高度な知的職種の一部を効率的に置き換える一方で、手作業や現場系の熟練職が「安定した職業」として再評価される現象は、労働価値のパラダイムが逆転し、知的労働がブルーカラー化していく可能性を示唆しています。
3)⚖️ 開発優先の国家戦略が生む「安全性・ルール」の課題
米国のAI導入のスピードは、中国との覇権争いを背景とした国家戦略と深く連動しています。
・安全性の後回し:
トランプ政権の「AIアクションプラン」に見られるように、米国政府は技術開発とスピードを優先する姿勢を強めています。
その結果、安全性や倫理・ルールづくり(例:AIによる著作権侵害問題など)の調整が後回しにされがちです。
・権威による警告:
この「開発優先」の姿勢は、AIの権威からも「国家間の熾烈な競争は、優位を保つためにAIの安全性を犠牲にする危険な動機を生み出し、公共の安全と国家安全保障上のリスクをもたらす」として強く警告されています。
若者の将来への不安は、こうした政策のスピード感と雇用の不均衡に起因しているとも言えます。
そもそも、AIが私たちの仕事を奪い、喪失するという予想が公表されてから既に10年以上経っています。
今回の米国における事情は、その証と言えるものですが、遡ってこうした現実を当然とも受け止めうることにもなったきっかけを再確認しておくことにします。
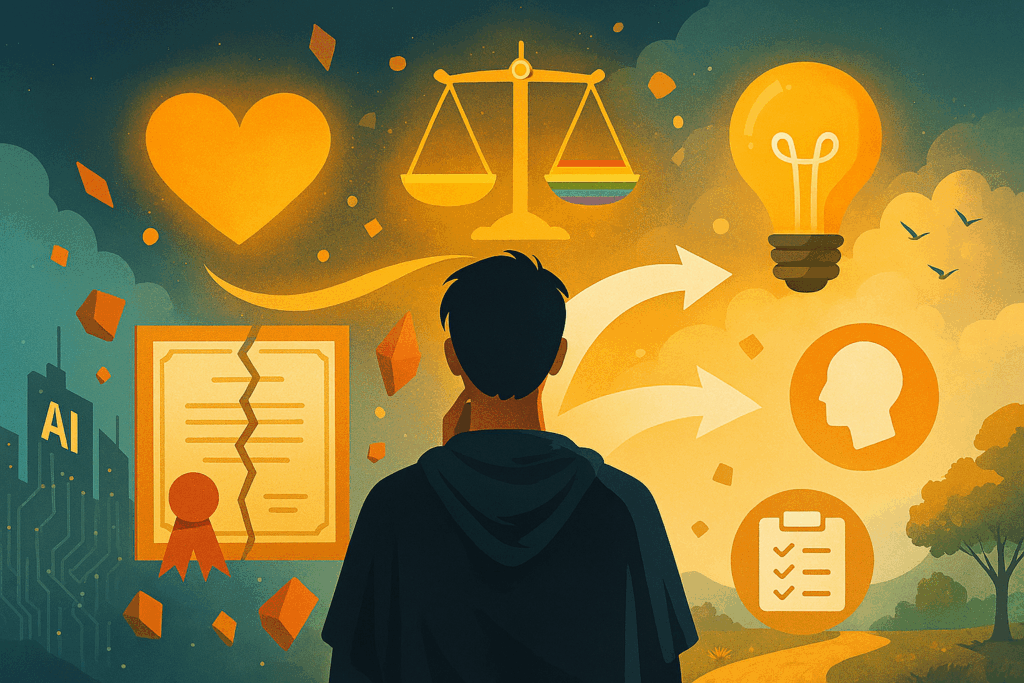



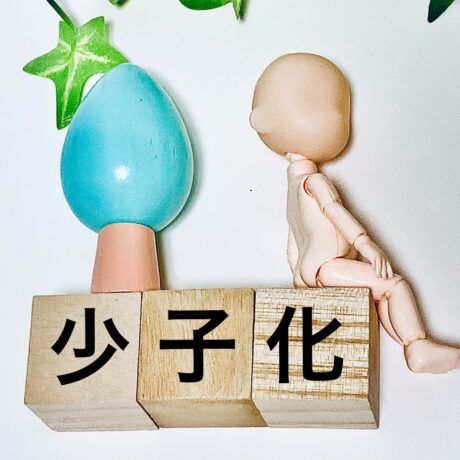
コメント