3.事業戦略としてのAIシフトの現状と今後|生成AIから超知能化へ、日本企業はどう進化するか
前章では、米国の異変を教訓に、日本社会が抱える構造的な課題(労働生産性の低迷、メンバーシップ型雇用の硬直性など)が、AI時代に顕在化するリスクを分析しました。
これらの課題を克服し、グローバル競争力を維持するためには、企業経営と事業戦略そのものにAIを深く組み込む「AIシフト」が不可欠です。
本章では、生成AIの登場を端緒として加速するAIシフトの波に対し、日本企業が現在、事業戦略、組織構造、人材開発においてどのように対応し、進化しているか、その現状と具体的な流れを整理します。
AIを「道具」としてだけでなく、「事業の軸」として捉え、競争優位性へと導く上での道筋を考察します。
1)普及期・社会実装フェーズに入った生成AI|通常業務と日常生活での「AI活用」
💡 生成AIの「民主化」「一般社会化」と業務効率化の初動
2023年以降、ChatGPT、Gemini、Copilotなどの高性能の生成AIツールは、わが国においても企業を初めとしてAIシフトを本格的に加速させました。
すでに日本の企業や自治体、教育機関において日常業務の一部として定着しつつあります。
・多くの企業では、まずバックオフィス業務や定型的な知的作業への導入が始まっています。
議事録の要約、メールや文書のドラフト作成、カスタマーサポートにおけるFAQ応答の補助などが挙げられます。
業務効率化が進行しています。
この段階では、AIは「労働力の代替」というよりも「生産性向上のための強力なアシスタント」として位置づけられています。
・個人レベルでの私的一般生活でも、ブログ作成、翻訳、学習支援、家計管理などの用途で利用が広がっています。
私もこの3つの生成AIを並行して、サイト運営に活用しています。
また、大学生の活用は当たり前になり、レポートや論文作成への活用は、教授・教官を悩ませることになっています。
・一部の自治体では、住民対応や文書作成支援などの実証実験が進み、行政サービスの質向上が模索されています。
この段階は、AIが「補助的な道具」として社会に浸透するフェーズであり、導入のハードルが下がったことで、裾野が急速に広がっています。
特別なプログラミング知識を必要とせず、誰でも簡単に利用できる「AIの民主化」「AIの一般社会化」を促進している段階と言えるでしょう。
🏢 現状の課題:活用範囲の限定と「AI慣れ」の不足
一方で、日本の現状はまだ試行錯誤の段階にあるとも言えます。
多くの企業では情報漏洩リスクへの懸念から、利用を限定的な部署や非機密情報に留めています。
また、AIが生成したアウトプットを適切に評価・修正・指示する「プロンプトエンジニアリング」や「AI慣れ」が組織全体に浸透しておらず、ツールを導入しても十分な効果が出ていないケースも散見されます。
2)企業固有の競争力強化フェーズへ|業種別AI活用の深化・専用化とその課題
次の段階では、各企業が自社の事業領域に特化した専用AIの開発・採用を進めており、企業力が試される段階にあると言えるでしょう。
📊 汎用AIから「専用AI」への戦略的深化
汎用的な生成AIによる効率化の先に、日本企業が目指すべきは、自社の競争優位性に直結する専用AIシステムの開発と採用です。
これは、特定の業務プロセスや顧客層に最適化されたモデルであり、自社が長年蓄積してきた独自データ(アセット)が学習の源となります。
例えば、
・製造業では、画像認識による品質検査や工程最適化にAIが導入され、熟練技術者のノウハウを学習したAIによる歩留まり改善など、熟練技能の補完が急速に進められています。
・金融業界では、過去の取引データを分析した不正検知システムの高度化などリスク評価と管理、資産運用、顧客対応にAIが組み込まれ、業務の自動化と精度向上が進行中です。
・医療分野では、診断支援や創薬シミュレーションにAIが活用され、専門知識とAIの融合が加速しています。
・小売・物流分野では、需要予測、在庫管理、配送最適化などにAIが浸透し、サプライチェーン全体の効率化が図られています。
🧱 戦略推進の鍵は「データ基盤」の整備
しかし、この戦略的深化を阻む最大の壁が、データのサイロ化(各部門にデータが分散し統合されていない状態)とデータクレンジング(データの品質を高める作業)の遅れです。
AIの性能は学習データの質に大きく依存するため、日本企業は今後、データ収集・統合・管理を行うデータ基盤(データレイクやデータウェアハウス)の整備を、AIシフトにおける最優先のインフラ投資と位置づける必要があります。
このフェーズでは、AIが「業務の中核」に入り込み、企業競争力の源泉として位置づけられ始めているのです。
3)AI技術の「事業化」フェーズ|独自開発と新収益モデルの創出へ
一方、日本企業による独自AI技術の開発も進んでいます。
但し、その目的は、自社・自組織内対応にとどまるものではありません。
🚀 技術をサービスへ転換する「AIアウトプット戦略」
AIシフトの最終目標は、単なる業務効率化に留まらず、AI技術そのものを収益を生み出す事業モデルとして確立することです。
これは、自社で開発した独自のAI技術やモデルを、顧客や他社にSaaS(Software as a Service)などの形でライセンス提供し、AIを活用したパーソナライズ性の高い新製品を開発するなど、新たな市場を開拓する戦略です。
例えば、NEC、富士通、ソフトバンク、Preferred Networksなどが独自の大規模言語モデル(LLM)やAI基盤技術を開発しています。
最近の日経掲載の例としては、以下があります。
⇒ サイバーエージェント子会社、IT大手も狙う「AI支援市場」参入 – 日本経済新聞 2025/10/3
⇒ NTTデータ、自律型のAIエージェント開発 営業部門向け – 日本経済新聞 2025/10/24
今日まさにこの記事が眼を引きました。
⇒ ソフトバンクとオープンAI、業務支援AIを展開 共同出資会社が発足 – 日本経済新聞
その他、スタートアップ企業によるAPI提供型AIサービスやSaaS型AIツールの事業化も活発化しています。
当然、産学連携による研究成果の事業化も進み、国際競争力を意識した技術開発が加速しているフェーズに入っているのです。
この段階では、AIが「収益事業」として確立され、技術そのものがビジネスの中心となることを意味します。
💰 日本が狙うべき領域:ドメイン知識との融合
海外の巨大IT企業(GAFAなど)が汎用的な基盤技術(モデル)で先行する中、日本企業は、医療、介護、製造業、インフラ管理といった、日本が世界的に高い専門性(ドメイン知識)を持つ分野で、現場の深い知見を組み込んだニッチトップのAIを開発し、その事業化を目指すべきです。
4)その次に進化する形とは|超知能化フェーズと未知の領域
今後、AIはさらに進化し、汎用人工知能(AGI)やマルチモーダルAIの登場によって「未知の領域」へと突入するとされています。
🌌 AI進化の予測不能性への対応
生成AIの次の進化は、より高度な推論や学習能力を持つ**「超知能化(Superintelligence)」**や、量子コンピューティングとの融合といった未知の領域へと進むと予測されます。
人間の知的能力を超える「超知能化」が現実味を帯びる中で、倫理・法制度・教育・雇用の再設計が不可避となる。
例えば、そこでは、以下のような対応・対策が不可避とされています。
・著作権、個人情報、責任所在などの法整備は依然として遅れており、AIガバナンスの確立が急務。
・AI人材の育成、社会的受容、教育制度の再編など、制度的対応力が問われるフェーズに入る。
こうした予測不能な進化に備えるため、日本企業は、目先の効率化だけでなく、基礎研究への投資や、異業種・大学とのオープンイノベーションを通じて、常に最先端技術の動向を取り込む姿勢を維持する必要があります。
🚀 日本の役割:技術と倫理の調和
AIが社会に与える影響が巨大化する中で、日本は、高齢化社会やインフラの老朽化といった独自の課題を解決するAI技術を開発し、その知見を世界に提供する役割を担えます。
また、AIの安全性や倫理的な利用に関する国際的なルール形成において、技術開発と倫理的利用の調和を目指すリーダーシップを発揮することが求められます。
この段階では、AIは「社会構造そのもの」に影響を与える存在となり、日本の制度設計力が試されることになります。
この項での「超知能」に関しては、一般論的な記述でとどめました。
現実的な状況を認識するためには、3段階目のフェーズに焦点を当てることが本稿の主意であるためです。
実は、「超知能」については、やはり日経記事をきっかけにして関係WEBサイト、ONOLOGUE2050で取り組んだ、以下の、記事があります。
参考にして頂ければと思います。
⇒ 【AIと人類の未来】日経『超知能』連載から深掘りする究極AIの衝撃と問い – ONOLOGUE2050 2025/6/14
⇒ Chat GPTとの対話で深掘りする「超知能」|日経『迫る大転換』第1回の読み解きと創作プロセス – ONOLOGUE2050 2025/6/15
⇒ Geminiと探る「超知能」の深淵:日経『迫る大転換』第1回とAI共創の記録 – ONOLOGUE2050 2025/6/16
⇒ 【2050年構想の羅針盤】日経「超知能」シリーズ総括からAIと人類の未来を考察 – ONOLOGUE2050 2025/6/20
⇒ 「人類拡張」とは何か──日経『超知能』シリーズとシン日本社会2050構想の接点 – ONOLOGUE2050 2025/10/8
5)AIシフトのボトルネック:人材育成と組織文化の変革
🧑💻 AIを「使う側」と「作る側」の人材不足
日本のAIシフトの成否は、技術導入以上に人材と組織にかかっています。
現在、企業内ではAIを開発・運用するデータサイエンティストやAIエンジニアが圧倒的に不足しています。
さらに深刻なのは、AIが出した結果を批判的に吟味し、業務に組み込むことができる全従業員の「AIリテラシー」の不足です。
この「AIを使う側」の能力向上が、導入したAIの効果を最大化するためのボトルネックとなっています。
🌱 不可欠な「心理的安全性」と「失敗許容の文化」
AIを導入し、新しい働き方を実現するためには、組織文化の変革が不可欠です。
AI活用による試行錯誤には失敗がつきものですが、日本企業に根強い失敗を避ける文化や縦割り組織は、AI導入のスピードを鈍化させます。
従業員が積極的にAIを試せるような心理的安全性の高い環境と、AIによる新しい働き方を歓迎するトップダウンのコミットメントこそが、組織全体でのAIシフトを成功させる基盤となります。
6)個人としてのAI技術と活用スキル向上への取り組み課題|セルフラーニングの薦め
AI社会において個人が自身の市場価値を維持・向上させるには、AIリテラシーの習得が必須であり、企業頼みではなく個人のセルフラーニングが鍵を握ります。
もちろん、そうした目的ではなく、自身の興味関心領域をAIの活用により拡張し、高め、思考と創造の満足度を高める上でもです。
個人の立場や目的別に応じたスキル向上への取り組み課題と簡単なガイドを例として取り上げました。
🔰 初級:AIへの抵抗感をなくす「基礎習得と実践活用」課題
初級レベルの最大の課題は、AIの「実態」を正しく把握し、自身の希望・関心レベルに応じて、抵抗なく使いこなすための基礎知識を入手・理解し、活用することです。
・AIの「できること」と「限界」の体感的な理解:
まずは、生成AI(ChatGPT, Geminiなど)を毎日使ってみる習慣をつけましょう。
ニュースの要約や学習用途で利用し、「プロンプト(指示文)」を工夫することで、AIの特性と限界を体感的に把握することが最優先です。
・AIに関する動向や情報の収集・知識の広がり:
AIが社会やビジネスに与える影響は日々変化しています。
メディアでAIに関する企業や社会的な動向を積極的に収集し、調べ、理解することで、自身の知識・知見を広げていきましょう。
AIがどのように産業や労働市場を変えつつあるのかを知ることが、次のステップに進むための動機付けになります。
・情報セキュリティと倫理的な利用の基礎:
AIを利用する際、機密情報を入力しない、著作権やプライバシーを侵害しないといった、基本的な情報セキュリティや倫理的なルールを理解し、実践することも必須になります。
💻 中級:業務へのAI統合と「検証能力」の課題
初級レベルでの課題をクリアしつつ、AIに慣れ親しんだら、次は日常生活でのニーズや自身の通常業務にAIをマッチングして組み入れ、実際に使いこなし、成果を出す段階と言える中級レベルに進みます。
<課題>:業務・関心領域へのAI統合と「検証・拡張能力」の確立
中級レベルでは、単なるAI利用から一歩進め、AIを業務フローや学習・創造プロセスに深く統合し、AIが出したアウトプットの実用性、真偽(ファクトチェック)、創造性を検証・評価するスキルが求められます。
ガイド:
・AIの「実務・創作ツール」としての活用:
Copilotなどのビジネス統合ツールや、画像生成AI、音楽生成AIなどを活用し、データ分析の補助、複雑な情報の要約・構造化、新しい企画のアイデア出し、創作活動の試作といった具体的な目的にAIを組み込みましょう。
・批判的思考(クリティカルシンキング)の訓練:
AIが生成したアウトプットについて、「これは本当に正しいか?」「より良い表現はないか?」と常に疑う姿勢を持ち、情報のファクトチェックを必ず行いましょう。
AIを盲信するのではなく、意思決定のパートナーとして活用する能力を磨きます。
💼 上級:戦略的な事業応用と「独自AI」構築による市場価値創造の課題
中級レベルで業務や関心領域の効率化・拡張を実現したならば、上級レベルでは、AIを自身の事業や専門領域における競争優位性の源泉に変える戦略的な活用を目指します。
<課題>:AIによる事業戦略への応用と「独自AI」構築による市場価値の創造
AI技術を自身の事業や専門領域における収益向上、時間の創出、または社会への新たな価値提供に直結させる能力が必要です。
これは、既存のAIツールを利用するだけでなく、特定の課題解決のためにAIを設計・カスタマイズする段階を指します。
<ガイド>:
・専門分野特化型AIの構築:
ノーコード/ローコードツール(例:カスタムGPT、特定プラットフォームのAIビルド機能)を活用し、自身の専門知識や独自データを学習させたパーソナルなAIモデル(例:専門分野の知識を提供するチャットボット、特定のタスクを自動化するAI)を構築・運用します。
・市場への価値転換:
構築した「独自AI」を、自身の個人事業の収益源や、専門職としてのコンサルティング価値に変える方法を探りましょう。
この段階では、技術的なスキルに加え、AI導入によるリスク管理や法規制への対応能力、そして「AIの作り手」としての視点が不可欠となります。
🧗 レベルアップへの助言
AIスキルは、一度学んで終わりではなく、日々進化する技術に適応していく継続的な学習の旅です。
初級者としてAIに対する抵抗感をなくし、中級に進んで自身の生活や業務での経験や成功体験を積むことが、AI社会における個人の生活とキャリアの大きな資産となります。
初級者の一部は、このようなセルフラーニングを通じて中級、そして上級へと必ず進んでいくことができます。
上級に進んだ個人事業主や専門職は、AIを道具としてだけでなく、ビジネスモデルそのものを再構築する戦略的なパートナーとして活用していくことになるでしょう。
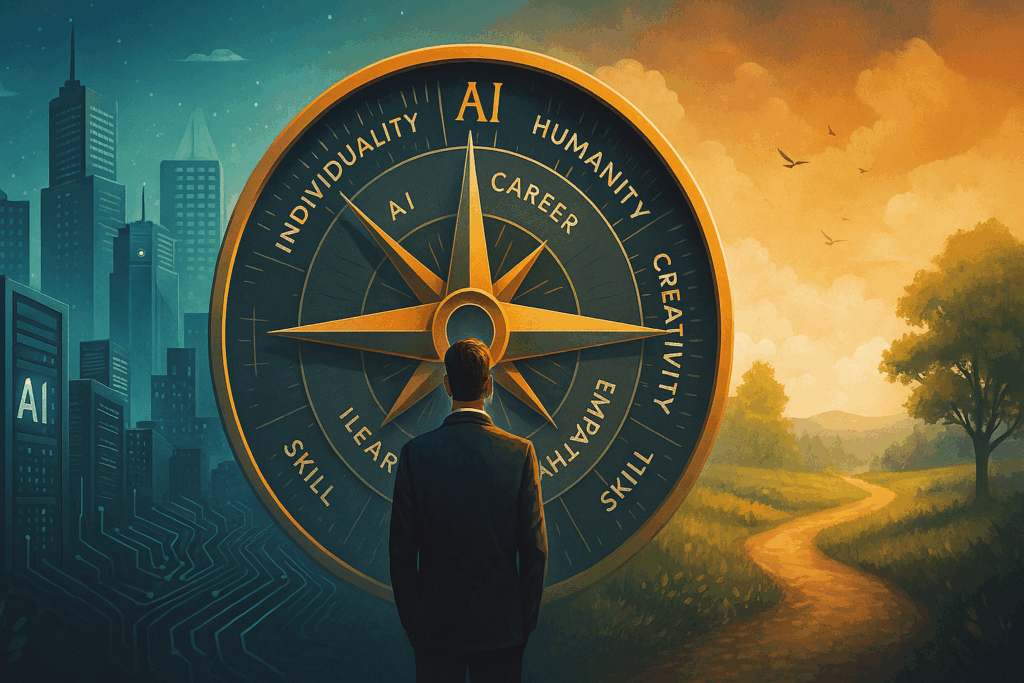



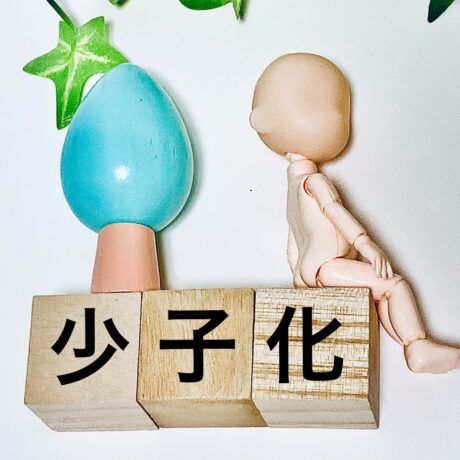
コメント