4.個人はシンAI社会時代の日本の労働市場と働き方変革にどう備えるか
前第3章で、私たちは生涯にわたるセルフラーニング(学び続けること)の重要性を認識しました。
では、その学習で得た力を、不安定化する日本の労働市場において、どのように具体的な「備え」へと変えていけば良いのでしょうか。
この最終章では、学歴や既存の職種に縛られることなく、AI時代を乗りこなし、自らの「生き方・働き方」を主体的に創造するための5つの具体的な戦略と、行動の羅針盤を提示します。
1)AI時代のキャリアクライシス:大卒・学歴依存から「スキル依存」への転換
米国の異変が示す日本の現実:不安定化する知識労働と流動性の高まり
米国で起こっている若年層の失業率上昇は、景気の波とは関係なく、AIが知的・定型的なホワイトカラータスクを代替し始めたことによる構造的な変化です。
長らくキャリアの保証とされてきた「大学の学位」は、もはや安定の代名詞ではなくなりつつあります。
日本も、終身雇用を前提とした「メンバーシップ型雇用」の曖昧さの中で、AIによるタスク代替の波が、大卒を含む個人のキャリアリスクを隠蔽しやすい状態にあります。
正社員として一つの会社に長く勤めるというモデルは揺らぎ、副業、フリーランス、プロジェクト単位の契約など、雇用形態の多様化が進んでいます。
こうして、個人の働き方はより流動性の高いものへと変わっていきます。
私たちはこの現実を直視し、「学歴ではなく、スキルと個性が価値を決める」時代へと軸が完全に移動しつつあることを認識する必要があるでしょう。
・大学進学を選択するなら「何を学ぶか」の意識変革
もし大学進学を選択するならば、その目的を「学位の取得」から「AIに負けない、人としての価値を高める能力の習得」へと切り替える必要があります。
知識習得から「問いを立てる力」へ:
AIが知識を提供する時代、大学は知識のインプットだけでなく、批判的思考(クリティカルシンキング)、倫理観、そして「そもそも何をすべきか」という本質的な問いを立てる力を徹底的に鍛える場となるべきです。
「学際性」の追求:
専門分野の知識に加え、哲学、芸術、歴史など、一見非実用的とされる人文科学的な視点を意識的に学び、AIでは不可能な新しい価値観を生み出す視点を身につけることが、将来のキャリアの土台となります。
2)創造性・共感性・倫理:人として、個人・個性の価値へのシフト・回帰
「仕事中心」から「価値中心」への転換と「人間らしさ」の再定義
AIが多くの定型業務を担うようになる時代には、仕事は「自己実現」や「社会との接点」として再検討・再定義されるべきでしょう。
「仕事=生活の中心」という価値観から、「どんな価値を届けたいか」という「価値中心」の働き方へと軸を転換する必要があります。
言い方・見方を変えれば、生きる上でどんな仕事を選択するか、働き方をデザインするかということになります。
このことは、特段新しい考え方ではなく、人としての基本ですね。
この転換期に個人が市場で価値を持つには、AIに代替されない「人間らしさ」にこそ、自身の個人・個性の価値、生き方の軸を置くことが望ましいと考えます。
・AIの限界が映し出す「人間固有の強み」
繰り返しになりますが、AIが知識・論理処理を担うほど、個人が市場で価値を持つには、「AIが苦手、あるいは不可能とする領域」にこそ、自身の個人・個性の価値を置くことの意味・意義が増します。
これは、AI時代だからこそ際立つ、私たち人類の本質的な能力そして生き方への回帰・シフトです。
もう少しこの視点で、考察を拡げて見ましょう。
共感性・人間性の深化:
他者の感情や痛みに寄り添う共感性、複雑な人間関係における繊細な調整能力は、AIが到達できない領域です。
医療、介護、教育、チームマネジメントなど、人間的交流が不可欠な分野で最も価値を発揮することになります。
非線形の創造性:
データや前例の延長線上にない、全く新しいアイデアや芸術的な感性、そしてユーモアや遊び心といった、個人の「ひらめき」や「好奇心」から生まれる創造力こそが、AIに代替されない付加価値となります。
倫理観と判断力:
AIが最適解を提供しても、その結果が社会的に、道徳的に正しいかを判断し、責任を負う「倫理的判断力」は、常に人間に求められる決定的で不可欠な価値です。
特にAIを悪用した犯罪が、グローバルレベルで急速に広がっている事態は、非常に憂慮すべきです。
善と悪のAIの闘いが、これからのAI社会の大きく、重い課題となっています。
🤝 協働型社会への移行とネットワーキン:
孤立しがちな働き方を避け、共感や対話を大切にする「協働型社会」への移行も求められ、重視されます。
異なる専門知識を持つ個人間やグループとの信頼に基づくネットワーク作りや、複雑な意見を調整し、協働を生み出す関係構築のスキル。
これらは、AI社会時代のプロジェクトを強力かつ有効・有益に推進する上で、極めて重要な「人としての価値」となるでしょう。
・「個性」を強みとして意識的に鍛錬する
あなたの持つ個人的な興味関心、哲学、そして他人にはない独自の感性こそが、AI社会における最高の資産です。
これらの「個性」を、単なる趣味や資質で終わらせず、専門スキルと同様に意識的に磨き、キャリアの軸とすることが、生き方・働き方を豊かにする鍵となります。
3) 「手に職」という原点回帰とAI共創:非大卒キャリアの新たな価値創造
・熟練スキルとAIの融合による「手に職」「技能」の復権・回帰
AI時代は、知識労働の価値を相対的に下げると同時に、「簡単に自動化できない現場の熟練スキル」の価値・必要性を再認識させています。
米国でブルーカラー職が再評価されているように、日本でも、配管工、大工、熟練の製造技術者など、現場での非定型な判断と手作業を伴う「手に職」の重要性は高まっています。
これは、単なる「復権」ではなく、AIを前提とした「手に職」「技能」という原点回帰です。
原点回帰ですが、現代の感覚や近未来への有効活用という視点を持ちたいものです。
AIを現場の「道具」として活用:
・熟練技術のAI学習:自身の熟練技術やノウハウをAIに学習させ、若手への技術伝承や業務効率化ツールを個人レベルで開発・活用する(例:カスタムGPTの構築)。
・現場判断力の拡張:AIによるデータ分析や画像認識を現場での判断(例:不良品検知、配管の最適ルート提案)に活用し、自身の熟練度をさらに高めるパートナーとします。
日本の伝統工芸やポップカルチャーとAIとの統融合:
陶芸、漆器、漫画、アニメといった日本の文化的な独自資産をAIの基盤データとして学習させ、新しいデザインの創出や、制作プロセスの革新(例:自動着色、素材提案)に活用する。
こうした個人の創造性と市場の拡張を目指す生き方・働き方は、これから一層求められ、価値創出に結びつくと考えます。
キャリアの選択肢の多様化と伝統工芸分野の専門校設置:
大学進学にこだわらず、職業訓練や専門学校でAIと融合する技術(例:データセンター管理、AI活用の設備保全)を身につけることが、高付加価値なキャリアを築く道の一つとなります。
前項とこの項の観点から、日本の大学や高専、いや高校レベルでも、伝統工芸・伝統文化技能分野の専門校が開設され、無償化されることが望ましいと考えます。
もちろん、この分野でのAIの活用・貢献も含んでのことです。
4)孤独な取り組みを避ける:リスキリング支援と社会制度の活用
個人のスキルアップを支える「支援の輪」を活用する
AI時代のキャリア変革や新たな形成は、個人だけの「孤独な取り組み」となることは、できれば避けたいものです。
生涯学習と「再スキル化」の必然性を認識することで、セルフラーニングの重要性は高まります。
しかし、それを支える企業や社会の支援を「自己成長」「自分であるため」のツール・機会として意識をもって活用するようにできればと考えます。
・「学び直し(リスキリング)」の支援を最大限活用する:
政府や自治体が提供する教育訓練給付制度や補助金を積極的に調査・利用し、AI関連のスキル習得に必要な費用を公的に支援してもらいましょう。
企業内のリスキリングプログラムや、AI関連資格取得支援があれば、自身の可能性や市場価値を高める機会として活用できればと思います。
・企業の「ジョブ型転換」をチャンスに変える:
企業がジョブ型に移行する際、自身の職務(タスク)が明確になるため、AIに代替されにくい「創造性・共感性タスク」を担うことができるようにしたいものです。
そのために積極的に提案し、自身の役割を主体的に再定義し、確認するチャンスとして活用したいですね。
・コミュニティを活用した学習と情報交換:
オンライン、オフラインを問わず、AI活用やリスキリングに取り組む仲間とのコミュニティに参加するのもお薦めです。
これにより、最新の情報や実践的な知見を得られるだけでなく、キャリアの転換期における精神的な支えとなり、孤独な取り組みを防ぎます。
AI社会の波は、私たちに「キャリアは誰かに与えられるものではなく、自ら選び、創り上げるもの」というメッセージを送ってきていると想像・想定することもできるのではないでしょうか。
社会の支援も活用しつつ、自身の「個性」「独自性」を武器に、セルフラーニングを工夫・継続することが、シンAI社会を生きていくための備えとなるとも思います。
5) 正面からAIを仕事・働き方の軸に設定し、エキスパートをめざす生き方
AIによる社会変革は、AIそのものを専門領域とする「エキスパート」に対する需要を爆発的に高めています。
AIはすでに、医療、金融、製造、エンタメ、そして伝統工芸に至るまで、すべての産業・事業分野の「基盤技術」になりつつあります。
AIを道具として使うだけでなく、その開発、運用、そしてガバナンスを仕事の軸に設定することは、最も市場価値が高く、将来性のある生き方の一つとなる可能性が高いでしょう。
AIエキスパートが担う主要な役割の広がり
AIを軸にするキャリアパスは、単なる「プログラマー」に留まりません。
・AI開発・設計者:
データサイエンティスト、AIエンジニア、機械学習エンジニア(MLOps)など、AIモデルの構築と運用を担う専門職。技術的な専門性を極めます。
・AIと事業の橋渡し役:
AIコンサルタント、AIプロダクトマネージャーなど、事業の課題を理解し、AI技術を組み合わせて具体的なソリューションを生み出す役割。高いビジネスリテラシーとドメイン知識が求められます。
・倫理・ルール形成の専門家:
AIガバナンス専門家、AI倫理学者など、技術の暴走を防ぎ、社会規範に沿った利用を保証するためのルール作りやリスク評価を担う役割。哲学や法律、倫理の視点が不可欠です。
グローバル課題と自身の興味関心を融合させる道筋
AI技術は、日本社会のみならずグローバル社会共通の課題解決の鍵であり、個人の興味関心をそのままキャリアに直結させる多様な可能性を秘めています。
・グローバル課題解決への貢献:
環境・エネルギー: 気候変動予測、再生可能エネルギーの最適制御、資源リサイクルルートの最適化など、地球規模の課題解決に直結するAIモデルの開発。
食料・農業: 精密農業(スマート農業)、病害虫予測、サプライチェーンの最適化など、食料安全保障に貢献するAIシステムの設計。
・自身の興味関心を仕事に:
全ての産業がAIと関係しているため、自分の興味関心がある領域(例:アート、スポーツ、歴史、まちづくり)とAI技術を組み合わせることで、多様な可能性を持つ独自のキャリアを切り開くことができます。
・未知の領域への挑戦:
AI技術はまだ発展途上にあり、脳科学、量子コンピューティング、宇宙開発など、多くの分野で未知の臨まれる領域が残されています。
こうしたフロンティア領域での研究や応用を軸に設定することも、極めて重要な生き方です。
エキスパートをめざすための具体的なステップ
この道をめざす場合、セルフラーニングに加え、体系的な学習と実践的な経験の積み重ねが不可欠です。
a. 基礎の確立(数学・統計):
AIの根幹である線形代数、微分積分、統計学といった基礎知識を固めます。これは、AI技術の進化に対応し続けるための土台となります。
b. 実践的な学習:
Pythonなどのプログラミング言語と、深層学習のフレームワーク(例:PyTorch, TensorFlow)を習得し、オンラインプラットフォーム(Coursera, Kaggleなど)でプロジェクトに挑戦し、実績を積みます。
c. ドメイン知識との融合:
単なるAI技術者で終わらず、医療、金融、製造など特定の産業の知識(ドメイン知識)とAIスキルを組み合わせることで、替えの効かない高付加価値な人材となります。
AIを正面から軸に設定し、エキスパートをめざす生き方は、最も厳しい継続的な学習と高度な専門性が求められますが、それに見合うだけの社会的な影響力と市場価値をもたらす、シンAI社会における最も確かなキャリアパスの一つです。
もちろん、何物にも代えがたい自己実現や社会的貢献をもたらすものになると思います。

終わりに:AIと共に、私たちが生き、創る近未来
シンAI社会とは、単に技術が進化する社会ではなく、「人間がどう生きるか」を根本から問い直す社会です。
私たちは、AIに仕事を奪われることに怯えるのではなく、AIを強力なパートナーとして迎え入れ、「人間らしい働き方」を再構築していく必要があります。
そのために、今できることは、「自分の価値観を見つめ直すこと」「学び続けること」「つながりを大切にすること」ではないでしょうか。
AI時代を生き抜くためには、学歴ではなく、個人の「スキルと個性」が価値を決めるという現実を受け入れること。そして、創造性、共感性、倫理観といった人間固有の価値をこれからのキャリアの軸に据え、「孤独な取り組み」を避けて社会の支援やネットワークを賢く活用する主体的な行動も大切と考えます。
但し、時には「孤独な取り組み」も必要であり、有効・有益ではあると思いますが。
AIが切り拓くシン社会2050の可能性
AIは、個人のキャリアを変えるだけでなく、平和や安全、そして環境、エネルギー、食料といったグローバル社会共通の課題解決や改善・変革を可能にする技術です。
この技術を適切に活用することで、ONOLOGUE2050で掲げる、シン安保2050、シン社会的共通資本2050、シン循環型社会2050といった理念の実現、ひいてはシン日本社会2050、シン・グローバル社会2050の実現に大きく寄与する可能性を持ちます。
この大きな変革を主導するのは、他でもない一人ひとり、特に若い世代の皆さんです。
AIを単なるツールとしてではなく、「シン・イノベーション2050」の軸として捉え、自らの個性と主体的な行動で、より良い近未来をデザインしていくことを強く期待する先行世代者(後期高齢者)です。
LIFE STAGE NAVIは、そうした一人ひとりの選択と変化を、これからも共に考えていきます。



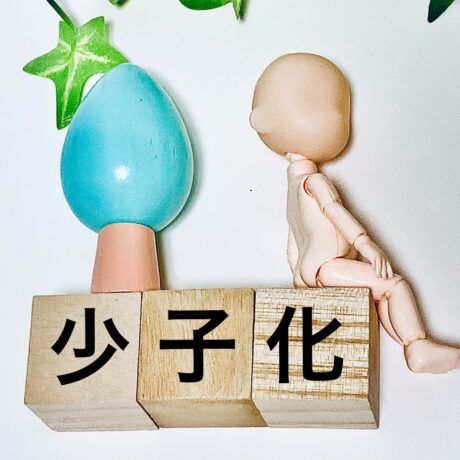
コメント