2.冨山和彦氏著『ホワイトカラー消滅』から考える|AI社会におけるリスキリングと教養の必要性
以前から「リスキリング」をどう考えるか、どう対処するかについて記事を、と考えていました。
それに当たって参考に、と考えていたのが、冨山和彦氏著の『ホワイトカラー消滅 私たちは働き方をどう変えるべきか』(NHK出版新書:2024/10/10刊)
AI化とその社会の進展で、ホワイトカラーという分類での仕事が消滅。
その時、私たちは働き方をどう変えるべきかを、特にリスキリングの観点から主張・提案します。
まず、同氏の基本的な認識と主張を以下、整理しました。
1)冨山和彦氏の主な主張とキーメッセージ|書籍・インタビュー・解説記事から
① ホワイトカラー構造の転換
・日本の従来型ホワイトカラー(終身雇用・年功序列・大企業中心のメンバーシップ型雇用)が、産業構造/技術革新(特にデジタル化・AI化)により大きな転換期にある。東洋経済オンライン+2NHK出版デジタルマガジン+2
・とりわけ、「調整/分析/資料作成/定型的ホワイトカラー業務」がAIによって代替され得るという警告。東洋経済オンライン+1
・一方、「現場・現業(エッセンシャルワーカー)」の価値が改めて高まるとし、これらの分野への人材シフト・スキル転換を提案。日本の人事部+1
② リスキリング/学び直し/スキルのアップデート
・変化の時代には、“今までのスキル”だけでは通用しなくなる。したがって、自らのスキルを再定義し直す「リスキリング」が必須。NHK出版デジタルマガジン+1
・ただし、リスキリング=“何でも学び直せばよい”という意味ではなく、「自分/企業がどこに価値を出すかを明確にして、それに沿ったスキルを学ぶ」必要があると指摘。note(ノート)
・また、企業が「多様な選択肢を用意しました。あとは個人で選んで学んでください」というような曖昧な形では、リスキリングは機能しないという批判も。日本の人事部
③ 基礎力・教養(リベラルアーツ)の重要性
・単に専門スキルを積むだけでなく、「考える力」「言語・論理の力」「知識を身体化・実践化できる力」といった基礎・教養が重要だと述べている。日本の人事部
・具体的には、言語系(日本語/外国語)、数理系(数学・簿記会計などビジネス言語)を“ビジネス上の言語”とも言い換えており、これらがあって初めて変化時代のスキルがうまく機能すると。日本の人事部
この中の「教養」「リベラルアーツ」とその内容・在り方について、非常に気になっています。
この視点が、次章以降の「スキリング」を重視する考えに結びつくことになります。
④ 個人の責任・主体性と変化への備え
・個人は「自分はどういう価値を出す存在になれるか」を自覚し、自らスキルやキャリアをデザインする必要がある。特に、“指示されたことをやる/試験で良い点を取る”だけのタイプ(=従来型ホワイトカラー適応型)は、AIと競合しやすいという警告。日本の人事部
・企業・教育機関・政府の役割も重要だが、個人が自分の今後を考えることを怠ってはいけないという強いメッセージがある。TKCグループ
⑤ 中小企業・現場価値の再評価/付加価値生産性
・中小・地域の現場にこそ今後の成長の余地があり、生産性向上・賃金上昇・高付加価値化が鍵になるという。TKCグループ
・そのためにも、DX・AI導入は手段であって、その前提として「どこが儲かるかを見える化」「仕事を切り分けて集中すべき領域を定める」などが重要だと述べている。
2) 『ホワイトカラー消滅』の大筋
次に、紹介した『ホワイトカラー消滅』の内容を、以下の2つの視点で理解・把握。
① 二つの危機が同時進行:「人手不足」と「人余り」の時代
・2040年に日本は約1100万人の人手不足(介護・医療・物流などエッセンシャル分野)に直面。
・一方で、AI・デジタル化により、事務・管理・専門職などホワイトカラー業務の8割が消滅しうる「人余り」が起きる。note(ノート)
→「人手不足」と「人余り」が同時に進む“ねじれ”が、長期のテーマ。
② 昭和型ホワイトカラー・モデルの終焉:
・メンバーシップ型雇用(終身年功・会社への所属で守られる身分)+東京の大企業ホワイトカラー中心というモデルは、人口減・グローバル競争・DXの三重苦の中で持続不能。
・キーワードは「アンラーン・リラーン・リスキリング」
3)リスキリング/スキリング論の核心
そして本稿の命題とした「リスキリング」及び敷衍した「スキリング」論に移る前の問題認識を、解釈を含めて以下整理しました。
① 「どの現場に移るか」が本質
冨山氏は、リスキリングを「今のホワイトカラー仕事を延命するためのツール習得」ではなく、
● ホワイトカラー余剰 →
● 人手不足のローカル・エッセンシャル分野への大規模な労働移転
を実現するための「キャリアの引っ越し」と位置づけています。ビジネス書要約ブログ -BYB-+1
・医療・介護・交通・物流・農業・インフラなどのエッセンシャルワーカーは構造的な人手不足。
・そこで働く人を「アドバンスト・エッセンシャルワーカー」として高度化し、付加価値生産性と賃金を引き上げ、新しい中間層の中心に据えるべきだ、と提案。ビジネス書要約ブログ -BYB-
これは、私が「どこで、何を仕事とするか」という課題と繋がっています。
② 「資格・教育システム」ごと変えるべき
・職業大学・専門職教育を重視し、「現場で通用するスキル」を体系的に育てる教育・資格制度へシフト。
・経営側も、「現場×テクノロジー」で生産性を上げることに本気でコミットしないと意味がない、と企業の意識改革を強く求めている。ビジネス書要約ブログ -BYB-
この課題は、次章以下の課題と繋がりますし、「これから何を学ぶか・どんな専門を選ぶか」という次世代のスキリングのテーマと相性が良い領域です。
それは、やはり、先に公開した記事の第4章と直結します。
⇒ 【AI時代の羅針盤】学歴に依存しない「生き方・働き方」へ!個人のキャリア変革と具体的備え – 4ページ目 (4ページ中) – Life Stage Navi
4)AI時代に「残る仕事/消える仕事」についての見方
①AIは「頭脳労働の代替財」
・旧来のDXは業務効率化の補完財だったが、生成AIは「脳機能そのものを代替する代替財」であり、ホワイトカラーの知的労働を根底から揺さぶる、と指摘。type
・データ処理・調査・定型分析・資料作成など、ファクトとロジックの勝負だけの仕事はAIが圧倒的に得意になる。
② 生き残る仕事の3条件(冨山氏の整理)
エンジニア向けインタビューなどで、AI時代に残る「良い仕事」の共通点として、次の3つを挙げています。type
・一次情報にアクセスする仕事:
顧客・現場・生身の人に直接会いに行き、情報を取りに行く仕事。
データ処理の価値が下がるほど、「現場・現物・現人」から生情報を取ってくる役割の価値が上がる。
・感情労働(エモーショナル・ワーク):
エンタメ、対面サービス、カウンセリング、マネジメントなど、人の感情に働きかける仕事。
BtoBでも最終意思決定の場面は、感情・信頼・関係性が効く領域で、人間が担い続ける。
・意思決定と結果責任を負う「ボスの仕事」
戦略・方針を決めてその結果を引き受ける仕事は、AIには委ねられない「最後の人間の領域」。
そして、これら3つを支えるものとして、
「知識の非対称性」ではなく「経験の非対称性」がキャリアを左右する
というメッセージを出しています。type
5)世代別の処方箋と教育への批判
①40〜50代ホワイトカラーへの警鐘
・大企業の事務・企画・管理職など、「昭和型ホワイトカラー街道を歩んできた層」ほどリスクが高い。
会社の内部ポジションにしがみつくのではなく、
・事業の「現場」に入り直す
・P/L責任や意思決定を引き受ける立場に移る
・ローカル企業・中小企業での現場マネジメントに転じる
といった「キャリアのジャンプ」を促している。ビジネス書要約ブログ -BYB-+1
②20〜30代へのメッセージ
・「大企業のホワイトカラー=安定」という発想は30年単位で簡単にひっくり返る常識に過ぎない、と強調。type
若い世代ほど、
・法務・財務・英語・デジタルリテラシーなどのポータブルスキル
・意思決定の経験を積める現場(スタートアップや地方中小の右腕的ポジションなど)
で「経験の非対称性」を作るべきだと説く。
③「ホワイトカラー予備軍」を量産する教育への疑問
・今の日本の教育は、「とりあえず大卒→ホワイトカラー」を大量生産し、将来の“余る人材”を増やしていると批判。ビジネス書要約ブログ -BYB-+1
代わりに、
・職業教育・専門教育の強化
・ローカル産業やエッセンシャルワークを前提にしたキャリア教育
など、最初から「どの現場で、どんな価値を出すか」を考える教育が必要だと主張しています。
この項の「世代別」提言は、次章の展開と間接的に通じていることは、読み進めていくと分かって頂けると思います。
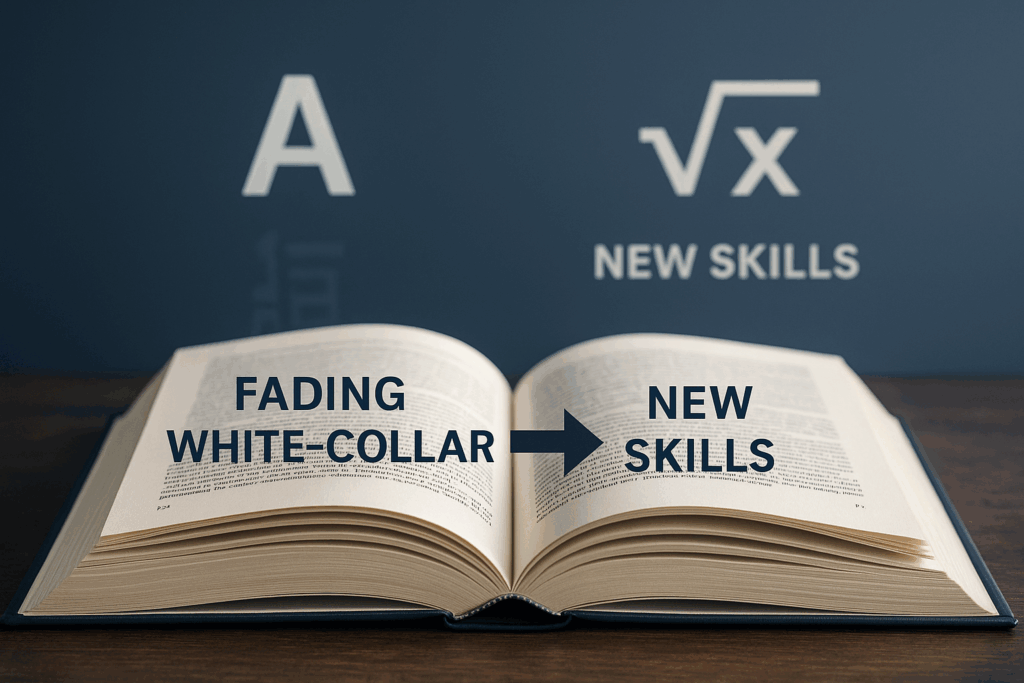


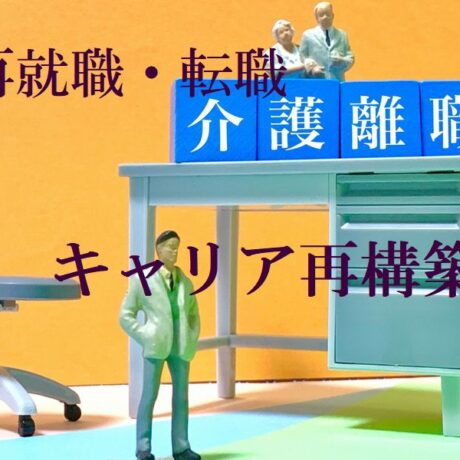

コメント