4.仕事は自分で創る|仕事はAIと共に創る時代へ
企業戦略としてAIシフトが進む中、従来の「会社から与えられる仕事」は消滅に向かうでしょう。
AI時代を生きていく上では、「自己の興味関心」や「社会のニーズ(人手不足)」を結びつけ、「仕事そのものを自分で創る」というマインドセットが極めて重要と考えています。
根源的ないくつかの問いを挙げて、AIとの関係性と重ね合わせて考えてみます。
1)何のために働くのか、どう生きるか?|自己実現と社会的貢献。自分のため、誰かのため
AI格差やリスキリングの議論は、ともすると「仕事を失わないための防衛策」のようなトーンになりがちです。
しかし、当サイトLife Stage Navi のテーマはあくまで「生き方・働き方」。
本質的には、「何のために働くのか」「どう生きたいのか」という問いから始める必要があります。
大まかにいえば、働く理由は
・自分や家族の生活を支えるため(自分のため)
・誰かの役に立ちたい、社会に貢献したいという思い(誰かのため)
の二つの軸で説明できます。
AIがいくら進化しても、人間の側からこの二つの軸がなくなることはありません。
むしろ、AIが単純作業を引き受けてくれるほど、「自分は何に心を動かされるのか」が問われていきます。
リスキリングもスキリングも、本来はこの二つの軸に結びついているときに、いちばん力を発揮するのではないでしょうか。
・自分や家族の将来を守るために、どのスキルが必要なのか
・誰かの困りごとを解決するために、どの知識や経験が生きるのか
という視点で学び直しを考えると、トレンドや不安に左右されるのではなく、自分なりの納得感のある学び方が見えてくると思います。
AIが定型業務を代替するほど、人間は「なぜ、この仕事をするのか」という根源的な問いと向き合わざるを得なくなる。
その目的は、先述したように見慣れ・聞き慣れしていますが、次の一般的な2つの用語、「自己実現」と「社会的貢献」に集約されるでしょう。
・自己実現の重要性:AIが事務的な作業から解放してくれます。そのため、個人は自分の興味関心、好奇心、得意なことといった「非定型でパーソナルな領域」に気持ち・エネルギーを集中することが可能になり、自己実現に近づく可能性が高まります。
・社会的貢献の価値:冨山氏の言う「エッセンシャルワーカー」への移動は、単なる食い扶持探しではなく、AIによって高度化された現場で「誰かの役に立っている」という強い実感を得られる、価値の高い仕事へと変貌します。
自分のため(自己実現)と誰かのため(社会的貢献)の接点と集合知に、AI時代に創造され、生きがいや働きがいを得る「仕事の種」があるのです。
AI時代のキャリアは、「AIに負けない仕事を探す」ことではなく、「自分が大切にしたい生き方に、AIをどう組み込むか」も考えるプロセスでもあります。
その視点を踏まえたうえで、次に「雇用」「労働」「仕事」の関係を整理してみます。
2)雇用と労働と仕事の関係
これまでの日本社会では、「雇用=労働=仕事」という図式が、長いあいだ暗黙の前提でした。
どこかの会社に正社員として「雇われる」ことが、そのまま「働くこと」「自分の仕事を持つこと」とほぼ同義だったからです。
すなわち、冨山氏が消滅するとした多くのホワイトカラーは、「雇用(会社への所属)」と「労働(与えられたタスク)」をほぼ同一視してきたのですが、AI時代にはこれが分離あるいは変質します。
・雇用:企業や組織と結ぶ契約の形(正社員・契約社員・業務委託など)であり、会社の「身分」や安定の源。しかし、AI時代の雇用は、「AI活用の戦略を実行できる人材を保持する枠」へと変化するでしょう。
・労働:時間や労力を提供する行為そのものであり、会社から与えられた具体的なタスク。AIが代行するため、人間が行う労働は「最終意思決定」「創造」「共感」の領域に集約されるでしょう。
・仕事:誰かのために価値を生み出す活動、役割。社会的価値を生み出す行為そのものです。これこそが、AIに代行されず、自分でデザインし、創り出すべき領域です。
会社に雇われていなくても、フリーランスとして「仕事」をしている人はたくさんいますし、家族介護や地域活動のように、「労働」ではあっても報酬が発生しない貢献もあります。
AI時代にキャリアを考えるということは、「雇用の形」だけに縛られず、自分なりの仕事の輪郭を描き直すこと、とも言えます。
日経記事が示したように、企業側はAIを前提に「雇用の中身」を組み替え始めています。
その変化に対して、私たち一人ひとりも、「自分はどのような仕事の仕方を組み合わせるのか(複業・副業・プロジェクト参加など)」という視点を持つことで、働き方の選択肢を広げることができます。
それゆえ、これからは、会社に「雇用」されていても、実態は「自営型プロフェッショナル」「エキスパート」として、自らの「仕事」を創り、提案し続ける姿勢が求められるでしょう。
3)興味関心・好奇心が生み出す仕事、働きと新しい職種・職務
新しい仕事や職種は、多くの場合、最初から「職業」として設計されたわけではありません。
誰かの興味・関心・好奇心から始まった活動が、ゆっくりと形を変え、「役割」になり、やがて「職種」と呼ばれるようになっていきます。
動画配信者、インフルエンサー、コミュニティマネージャー、オンライン講師…。
こうした職業の多くは、20年前にはほとんど存在しませんでした。
最初は「趣味」「遊び」「ボランティア」に近い形で始まり、それが価値として認識されることで、仕事として社会に認められていきました。
AI時代の良いところは、好奇心にもとづく小さな試みを、以前よりもずっと低いコストで形にできることです。
興味のあるテーマについて情報収集をし、簡単な資料や企画書をつくり、SNSやブログで発信してみる。
その過程の多くをAIが手助けしてくれます。
もちろん、AIにすべて任せるのではなく、
・自分が本当におもしろいと思うポイントはどこか
・誰のどんな困りごとを解決したいのか
を自分の言葉で考え続けることが前提です。そのうえで、「小さな試み」を繰り返すことで、自分だけの仕事の種を育てていくことができます。
AI時代に残る冨山氏のいう「一次情報」「感情労働」「意思決定」の仕事は、個人の強い興味関心から生まれる可能性を秘めています。
例えばAI時代における「興味関心事」を設定した場合の、Geminiの手?を借りて、新しい職種・職務の例を一覧にしてみました。
| 興味関心 | AI時代に生まれうる新しい職種・職務 |
| 人とのコミュニケーション | AI活用型カウンセラー:AIの分析結果(データ)を、共感力(感情)で橋渡しする仕事。 |
| 現場・地域創生 | アドバンスト・フィールドマネージャー:地域課題(人手不足、物流、農業)にAI/DXを導入し、現場の生産性を高める経営視点を持った現場監督・ディレクター。 |
| データ・知的好奇心 | プロンプト・戦略家:AIから「質の高い一次情報」や「新しい戦略」を引き出すための、質問設計の専門家。 |
こうした新しい職種・職務の芽は、必ずしもすぐに生活の糧にはなるとは限りません。
それでも、AI社会で「仕事を自分で創る」感覚を持てること自体が、今後のキャリアにとって大きな財産になります。
4)AIとの共創社会へ|AIとの付き合い方、活用の仕方
最後に、AIとの付き合い方について考えてみます。
日経記事でも、NTTが「5年後には業務の半分以上をAIが代替する」と語っているように、AIはもはや「導入するかしないか」を議論する段階を過ぎました。
これからは、どう付き合うかの問題です。
私たちが目指したいのは、AIを単なる効率化ツールとして使い倒すことではなく、「共創のパートナー」として位置づけることです。
具体的には、
・アイデア出しや仮説づくりの相棒として使う
・自分の考えを文章や図解に落とし込むサポーターとして使う
・わからないことを調べる第一歩として使う
といった形が考えられます。
一方で、
・最後に責任を負う意思決定
・他者との信頼関係の構築
・自分の価値観にもとづいた選択
といった部分は、人間にしか担えません。
ここを手放さずにいる限り、AIとの共創は、私たちの仕事や生き方の幅をむしろ広げてくれます。
AIは競合相手ではなく、最強の「共同創業者(Co-Founder)」「共同創造者(Co-Creator)」として付き合うべき存在と言えるでしょう。
あるいは、最も近くに、常に、存在する協力者、サポーター、アシスタントと表現するのも良いと考えます。
AIによる「競争」社会ではなく、AIで創出する「共創」社会の生き方・働き方を、と思います。
もう一度簡単に整理しました。
・AIとの付き合い方・基本スタンス:
AIを「答えを出す機械・システム」ではなく、「自分の思考を増幅するツール・システム」として活用し、付き合いたいものです。
・活用の仕方:
定型的な知識の収集や分析はAIに任せつつ、人は「結果の解釈」「倫理的な判断」「人間的な感情の訴求」という、価値を生む最終工程に集中・集約することが肝心です。
ただ、そこに至るまでの思考のキャッチボールは、うまく行いたいですね。
AIの計算能力(知識)とスピーディーな対応力、人間の判断力とイメージ力(教養)の接点・境界線を見極め、考察を深めていきます。
そうして、納得のいく、満足感が伴うアウトプット、新しい価値や達成感を創出することをめざしたいものです。
AI時代に仕事が消滅するのではなく、「人間がやるべき仕事」「やりたい仕事」が研ぎ澄まされ、一層磨かれ、これまでとは異なる新しい輝きを得ることになるでしょう。
この新しい社会を生き抜くための羅針盤が、自己固有の「スキリング」です。
そのために「何を学び、どう生きるか」という主体的な問いから始まります。
第3章で見てきたように、世代や現在地点によって、スキリング・リスキリングの焦点は変わります。
ただ、「仕事を自分で創る」「AIと共に創る」という視点は、どの世代にも共通する支えになることを再確認しておきたいと思います。
次に、本稿のまとめでは、ここまでの議論を振り返りつつ、Life Stage Navi らしい「AI時代の生き方・働き方」へのメッセージを整理してみたいと思います。
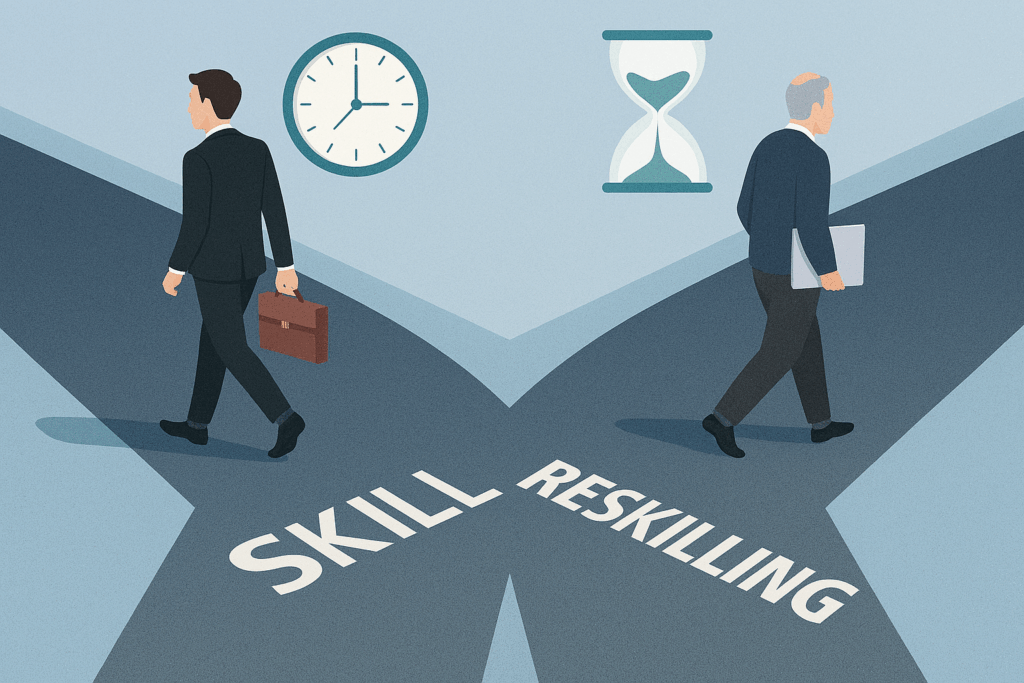
まとめ
1.AI格差による雇用選別の時代:日経記事要約
2.冨山和彦氏著『ホワイトカラー消滅』から考える|AI社会におけるリスキリングと教養の必要性
3.年齢・世代、現在地点の違いとリスキリングの考え方
4.仕事は自分で創る|仕事はAIと共に創る時代へ
以上の構成で進めてきた本稿でした。
テーマはシンプルに言えば「AI社会、AI時代におけるスキリングとリスキリングのあり方」になります。
そのめざすものとして、「自分固有のAIの活用と、自分固有の仕事や働き方を創造し、実践する生き方へ」
としたいと思います。
そのための出発点は、「自分の興味関心・好奇心を、AIを活用しつつ、仕事や働き方と結びつけていくこと」にあります。
その基本的な姿勢や心持ちは、年齢・世代に拘わらず共通するものですが、残念ながら個々人が持っている時間資源は異なります。
その前提のもと、生き方と働き方を、現時点での自身の確認と、これからの自分の想像・想定とを重ね合わせて考える機会を持って頂ければと思います。



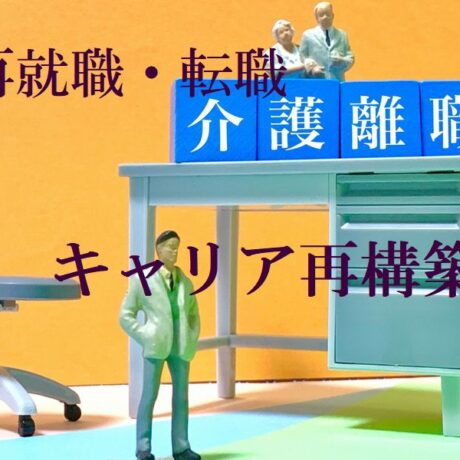

コメント