子育て罰(チャイルド・ペナルティ)とは何か|賃金格差・教育格差・制度の壁を超えて考える希望の処方箋
はじめに|子育て罰(チャイルド・ペナルティ)は日本社会のひずみの一つ
今、「子育て罰(チャイルド・ペナルティ)」という言葉が、私たちの社会の根底にあるひずみを照らし出しています。
子どもを持つという喜ばしい選択が、なぜか経済的な負担やキャリアの停滞、さらには親や子どもの生きづらさへと直結してしまう現象です。
これは、単なる個人の選択の問題ではありません。
子育て世代が直面するこの深刻なペナルティこそが、日本の少子化の重要な一つの要因であり、持続可能な社会の実現を阻む根深い構造的問題と考えてもよいのでは、とも思います。
日経記事(2025/11/8)から見える問題意識
先日、日経新聞に掲載された立命館大学教授・筒井淳也氏の記事(2025年11月8日付)は、この問題に鋭く踏み込んでいました。
ノーベル経済学賞受賞者クラウディア・ゴールディンの研究を引き合いに。
長時間労働や突発的な対応を求める日本の“オンコールな働き方”が、子育て中の親、特に母親のキャリアと賃金をいかに蝕んでいるかを指摘しています。
さらに、日本における「子育て罰」の格差は他国よりも特段に大きい、という厳しい現実も突きつけました。
(参考)
⇒ (今を読み解く)育児で賃金減る「子育て罰」 他国より日本の格差大きく 立命館大学教授 筒井淳也 – 日本経済新聞
なぜ今あらためて「子育て罰」を考えるのか
この問題は、もはや「子育て世代だけの問題」ではありません。
・子どもを持つことに躊躇する未婚・ディンクス世代。
・孫の世代の苦労に思いを致すシニア世代。
・そして、将来を担う子ども自身。
日本の社会に、この「罰」が生み出す負の連鎖によって、希望を失いつつある人々が存在するのです。
ある人が言う「希望格差社会」の一端です。
特に、経済的なペナルティに留まらず、子どもの教育格差やヤングケアラー問題といった、「子どもが受けるペナルティ」にまで議論を広げることが必要と、当サイトでは考え、本稿で考察することにしました。
本記事で扱う内容(親/子/制度/価値観)
本記事では、このチャイルド・ペナルティを、単なる賃金格差としてではなく、親(母・父)・子ども・制度という三つの視点から考察します。
具体的には、
・問題の起源(デンマーク、ゴールディン研究)と日本の特殊性。
・賃金低下、キャリア断絶、非正規集中といった親(母・父)への構造的なペナルティ。
・貧困の世代間連鎖、教育格差といった子どもが受ける、見えにくいペナルティ。
・保育制度、税制、縦割り行政など、日本の制度的課題の深層。
・そして、少子化対策を真に進めるために必要な働き方と価値観、そして社会システムの抜本的改革。
などの視点です。
LIFE STAGE NAVI を見て頂ける方々にとっての意味
様々なライフステージにある『LIFE STAGE NAVI』をお読み頂く方々にとって、「子育て罰」は無関係ではありません。
私たちは皆、子を産み育てる人、その支援を担う家族・友人、働く人を雇う企業人、そして近未来を築く社会の一員です。
このペナルティを理解し、解消に向けて行動することは、私たち一人ひとりが「多様な生き方を尊重する社会」という、難しいパズルを解くための一歩となります。
本記事を通じて、「子育て罰」という名の鎖を断ち切り、希望あるこれからと近未来を共に考えていくことにしましょう。

1. チャイルド・ペナルティとは何か|歴史・起源と3つの主体
チャイルド・ペナルティという概念は、単に「子育てはお金がかかる」という話で終わるものではありません。
これは、子育てという社会的に価値のある行為が、個人の経済的・社会的地位に負の影響を与えるという、構造的な矛盾を指し示しています。
言い方を換えれば、生き方・働き方に関わる重要な問題ということです。
1)デンマーク研究と用語の起源
「チャイルド・ペナルティ(Child Penalty)」という言葉が学術的に注目されたのは、北欧の福祉国家デンマークを対象とした研究がきっかけでした。
デンマークは、手厚い公的保育制度や男女平等を推進する政策で知られています。
しかし、2000年代のコペンハーゲン大学などの研究者による分析では、第一子の誕生を境に、母親の生涯賃金が父親と比較して大きく低下することが明らかになりました。
この発見は、福祉制度が充実しているはずの北欧ですら、女性のキャリアと賃金が「子育て」によって不可逆的な打撃を受けているという事実を突きつけました。
そして、「チャイルド・ペナルティ」という言葉を一気に世界に広めることとなったのです。
男女賃金格差の緩和に取り組む国々にとって、これは「いまだに倒せないラスボス」として立ちはだかっています。
2)ゴールディンの研究と“母親ペナルティ”
2023年にノーベル経済学賞を受賞した経済学者クラウディア・ゴールディンは、著書『なぜ男女の賃金に格差があるのか』において、このペナルティの要因を深掘りしました。
彼女が特に注目したのが、高い賃金が得られる職種に共通する「オンコール」(呼び出し可能)体制です。
以下、簡単に説明しましょう。
・オンコール・プレミアム:夜間や週末、突発的な事態にも「柔軟に」対応できる働き方(Greedy Jobs:貪欲な仕事)に対して、雇用主は高い賃金(プレミアム)を支払います。
対応できない人には、反対の作用が起きます。
・ペナルティの発生:子どもが生まれ、家庭内で「オンコール」なケア対応が必要になると、親(多くの場合、母親)はこの仕事側の「オンコール」に応じられなくなります。
結果、高いプレミアムが得られなくなり、それがそのまま「母親ペナルティ(Motherhood Penalty)」として現れるのです。
これは、働き方そのものが「家庭」と「仕事」の二者択一を迫る構造にあることを示しています。
3)日本での「子育て罰」という社会語の成立
日本においても、経済学的な賃金ペナルティの研究は以前からありましたが、末冨芳氏・桜井啓太氏の共著『子育て罰』(光文社新書・2021年)のヒットにより、この問題が一般社会に広く浸透しました。
この書籍が広めた「子育て罰」という言葉は、狭義の賃金格差に留まらず、子育て世代への公的支援の小ささ、社会的無理解、生きづらさといった、より広範な社会的・政治的要素も含んだ概念として認識されることになりました。
日本のペナルティの深刻さは、単なる市場原理だけでなく、制度や社会の冷たさによってもたらされている、という問題意識が根底にあります。
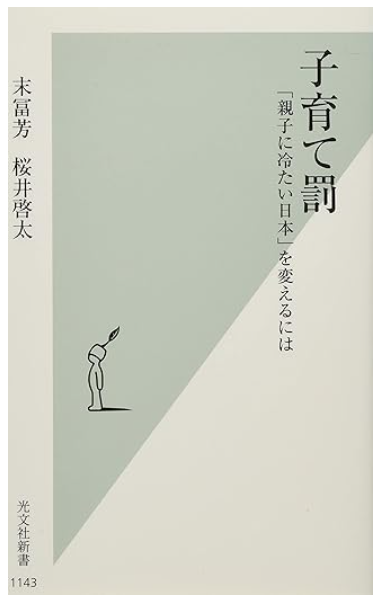
4)親(母)・父・子どもの三方向のペナルティ
チャイルド・ペナルティは、主に「母親」の賃金低下として語られてきましたが、その影響は三方向に及んでいます。
| 主体 | ペナルティの具体例 |
| 母 | 賃金低下、キャリア断絶、非正規雇用集中、昇進の遅れ |
| 父 | 長時間労働の固定化、育児・家庭生活への関与困難、父親ペナルティ(育休取得による評価減や賃金影響) |
| 子ども | 親の所得低下による教育格差、時間的貧困、親のストレスによる影響、貧困の世代間連鎖 |
そして、「子育て罰」の最も大きな問題は、罰を受ける主体が親だけではなく、子ども自身にも及ぶ点にあります。
特に日本では、親の所得や時間が子どもの機会に直結する傾向が強く、第3章で詳述する「子どもが受けるペナルティ」が深刻です。
5)日本の特殊性:ダブルケアと長時間労働
日経記事でも指摘された通り、日本のチャイルド・ペナルティは他国と比較して特段に大きいことが研究で示されています。
その背景には、ゴールディンが指摘した「オンコール」な働き方を超えた、以下のような、日本独自の複合的な要因が存在します。
① 無限定な働き方の要求
日本では、労働時間だけでなく、「転勤・異動の拒否をしない」ことや「職務内容の変更に柔軟に応じる」ことが高賃金(総合職)の前提とされてきました。
この無限定性こそが、育児による時間的・地理的制約を持つ親を、高賃金コースから弾き出す最大の要因となっています。
② 深刻なダブルケア問題
高齢化先進国である日本は、育児と同時に親の介護が始まる「ダブルケア」の時期が早く、その負担が女性に集中しがちです。この相乗要因が、女性のキャリア断絶をより深刻なものにしています。
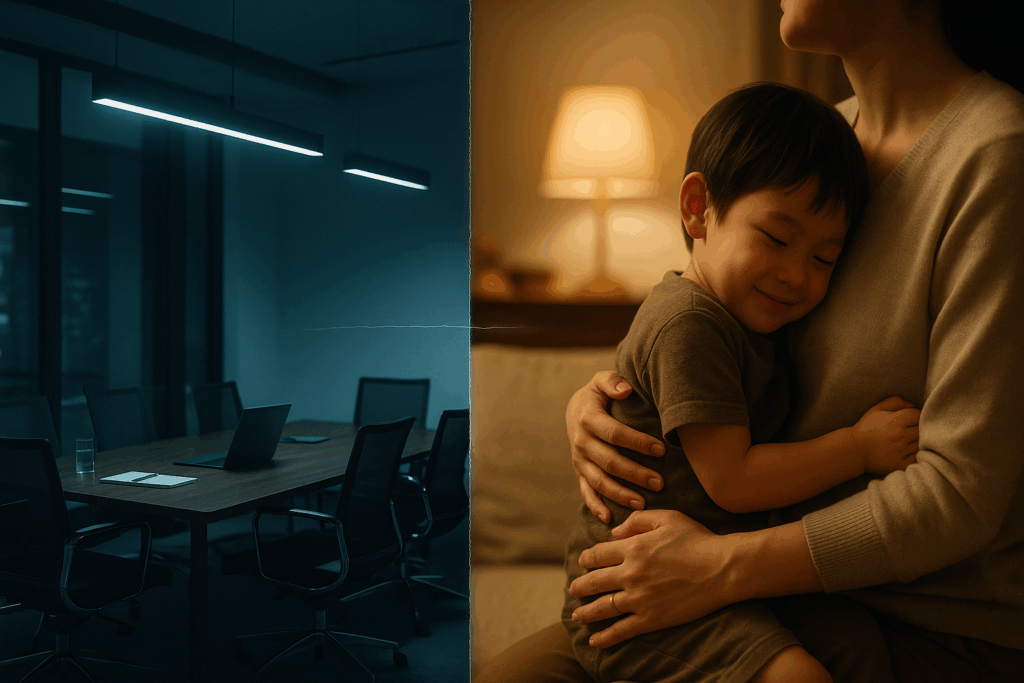


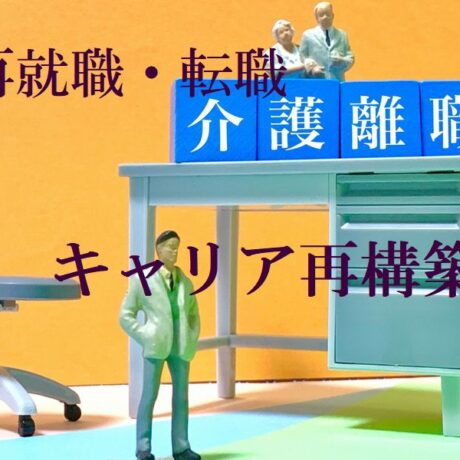

コメント