6. 解消は可能か|働き方・企業文化・価値観・制度の改革
チャイルド・ペナルティの解消は「とてつもなく難しいパズル」であり、個人個人の事情・実情がその数だけ多様かつ複雑です。
そのためには、働き方、企業文化、そして社会全体の価値観と制度を、根底から問い直す抜本的な改革が必要です。
一応、一般論的に俯瞰し、整理しておきましょう。
多くは、ここまでの考察の繰り返し、確認になるでしょう。
1)働き方の“オンコール性”の見直し
ペナルティの根源である「オンコール」な働き方からの脱却が、企業サイドの対応を要求する点、政策化することは可能です。
これは、親の仕事と家庭の両立を可能にし、ペナルティを直接的に軽減する核心をなす取り組みです。
以下、その例を挙げました。
・「脱・長時間労働」の徹底:残業規制の徹底に加え、業務のムダを排除し、生産性を高める意識改革が不可欠です。
・時間と場所の柔軟性:フルフレックス制度やリモートワークの活用を、単なる福利厚生ではなく、標準的な働き方として定着させることが重要です。
ここからイメージできるのは、やはり、それが可能なのは、大手企業と先進的な企業に限定されることです。
2)評価制度・企業文化改革
制度を変えるだけでなく、人が働く企業文化と評価基準を変えなければ、ペナルティは解消されません。
その視点から、次のような問題や傾向は、これまでも、現在も、強く指摘されています。
・「時間」ではなく「成果」で評価:長時間働く社員を評価する慣行を止め、育児などで時間制約があっても成果を出している社員を正当に評価する仕組みを構築します。
・アンコンシャス・バイアスの排除:管理職や社員一人ひとりが持つ、性別や子育てに関する無意識の偏見を研修などで是正し、キャリア機会の公平性を確保します。
ここでもやはり、企業責任を強制することになり、影響力・成果は、限定的になります。
3)行政・地方自治体の限界
公的な支援が、当事者のニーズに合わせて切れ目なく提供されるよう、国及び地方自治体、行政側の改革が絶対条件です。
一般的な改善改革政策のイメージは以下でしょうか。
・子ども家庭庁の機能強化:文科省や厚労省に散らばっていた子育て関連予算・権限の一元化を強力に進め、真に利用者(親・子ども)視点に立った制度設計を確立する必要があります。
・地方自治体の一般的政策:保育所などの受け入れ施設の増強や親への金銭的支援など、一般的な子育て支援策として打ち出されています。しかし、当然、財源と人材の問題は、払しょくされることがありません。
・地域コミュニティの再生:子育て支援を、行政サービスだけでなく、地域住民やNPOなどが支える「地域の子育て力」を再生させる取り組みが必要です。
そこでは責任と実行力が問われるのですが、制度・政策自体の多くが、企業に押しつけ、委ねるものであり、自ら責任を取ること等あり得ません。
当然自治体は、繰り返しますが、財政不足と人く材不足、両面の呪縛から解放されることもなく、画餅以前に、画そのものを描けないケースも大いにあるでしょう。
そして、必ず、社会性・社会的側面から、前項のように、「地域コミュニティ」など行政外の「社会性」に政策展開(転換?)を図るのも常套手段になっています。
藁にもすがる思い、というと大げさであり、失礼とは自覚していますが、そう考えています。
4)少子化時代の家族観とケア観のアップデート
ペナルティの根底にあるジェンダー規範や家族観といった、社会の価値観そのものをアップデートする必要があります。そう簡単ではもちろんありませんが。
その背景や現実の一端を挙げました。
・ケア責任の共有:ケアは女性だけの役割ではなく、夫婦、家族、そして社会全体で共有すべきものであるという意識を確立します。
しかし、こうした「社会」とは、一体どういうものか、具体的な主体や当事者はだれか、など議論が必要です。
・多様な家族形態の尊重:子どもの有無や、家族の形態に関わらず、多様な生き方を尊重する社会観を持つことが、「子持ち様」といった対立的な言説を乗り越える鍵となります。
ここでも「多様」という便利な言葉を持ち出していますが、個人個人、個々の家族にとっては、選択肢や現実は唯一であり、多様というほど選択肢が存在するわけではありません。
一人ひとり、人の数だけ多様である、ということに他なりません。
5)子どもの社会的権利を重視した制度設計
ペナルティ解消の最終目標は、親の苦しみだけでなく、子どもが健やかに成長する権利を社会が保障することにあります。ここでも「社会」とは何か、誰かの明確な定義が必要です。
ここでその問い問答を始めると考察が進まないので、一応一般的な社会の責務という視点から、以下、この社会的権利に対する社会システムの例を挙げます。
・子どもの権利条約の徹底:子どもの最善の利益を優先する視点を全ての政策決定に反映させます。
・子どもへの直接支援:親の経済状況に関わらず、全ての子どもが等しく教育、医療、生活の機会を得られるよう、子ども自身への公的投資を大幅に増やします。
最後に|親ガチャ型「チャイルド・ペナルティ」解消の唯一の政策とは
「チャイルド・ペナルティ解消は社会責任」という無責任論と親ガチャ帰結
ここまで、一般論としての考察とその影響力のなさ、少なさの議論・考察に終始してきたような感がありますね。
ただ、チャイルド・ペナルティ解消の議論は、究極的には「子育ての費用をいかに社会全体で賄うか」という問題に行き着くのではと考えています。
この時、やはり一般論としては、その財源をどうするかとなり、結局、所得再分配の問題へと、行きつ戻りつ、になってしまうの常道です。
この議論にとどまる限りでは、今までがそうであったように、ほとんど何も変化しないでしょう。
チャイルド・ペナルティは、結局「親ガチャ」に尽きることに。
「時間とお金」が解決するチャイルド・ペナルティ対策と同質の課題
少子化対策も、子育て政策も、ほぼ同次元、同サイクルの問題と考えるのです。
「時間とお金」の問題は、その有無や程度を前提条件とした、「生き方」と「働き方」の問題と直結しています。
現状のような「労働市場」や「雇用システム」では、賃金や雇用形態が、簡単に望むように一大変革するはずがありません。
財政規律主義を前提とした議論も、結局、富裕層から徴収する、金を持っている人から徴収する方法しかなく、問題なくそれが実現することもありません。
可能ならば、当の昔に実現しているはずでしょう。
しかし、金があれば、時間は買えます。
お金で、他者や事業者の時間を買うことで、自分が望む生き方、働き方が可能になる人も増えるでしょう。
チャイルド・ペナルティの要因を抑制・軽減し、その効果的な対処・対応・対策の選択肢も現実的に見えてくるでしょう。
子育て・保育・教育も、親は親の立場で、意思決定できるほど成長した子は子なりに。
親にも子にも、仕事の有無・働き方にも無関係・無条件に支給するシン・ベーシックインカム
そこで取るべき政策、効果が見込まれる政策。
それは、すべての国民に無条件で給付する「ユニバーサル・ベーシックインカム」です。
ただ、従来の理念・概念、議論の範囲・範疇のベーシックインカムではなく、まったく新しい理念・概念・システムによるシン・ベーシックインカムです。
その詳しい考え方と内容は、以降2026年内に提案しますが、現時点でその参考になる考え方を示したWEBサイト及び公開記事があります。
以下をご覧頂ければと思います。
⇒ベーシック・ペンション法(生活基礎年金法)2022年版法案:2022年ベーシック・ペンション案-1 – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
⇒少子化・高齢化社会対策優先でベーシック・ペンション実現へ:2022年ベーシック・ペンション案-2 – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
⇒マイナポイントでベーシック・ペンション暫定支給時の管理運用方法と発行額:2022年ベーシック・ペンション案-3 – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
⇒困窮者生活保護制度から全国民生活保障制度ベーシック・ペンションへ:2022年ベーシック・ペンション案-4 – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
すべての子育てを担う親とその子が最低限の生活と保育・教育に必要な費用を保証される所得保障制度である、シン・ベーシックインカム(NBI)。
NBIが、働き方の選択を可能にし、親として希望する時間を持ち、子との関わり方も選び、子も、学びたいことを学ぶことも可能にするでしょう。
そしてそれは、結婚や子どもを持つ上での安心の提供と将来への不安の解消にも結びつくでしょう。
加えて、その生活を通じて、べーーシックな領域での支出が安定的に行われ、社会経済の安定的な活動と循環にも寄与することになります。
今後の関連課題における投稿に関心をお持ち頂ければと思います。
なお、以下の既出記事も参考になればと思います。
⇒ 給付付き税額控除とは何か|制度の意義・課題・限界と「シン・ベーシックインカム2050」構想の展望 – ONOLOGUE2050 2025/10/16
⇒ 「全額給付制」へ移行した海外の教訓|給付付き税額控除の「煩雑さの罠」と日本独自の「シンBI」への道 – ONOLOGUE2050 2025/10/31
⇒ 社会的共用資本としての送配電網:市場原理を超えた国有化と「シンMMT」新財源モデル – ONOLOGUE2050 2025/11/24


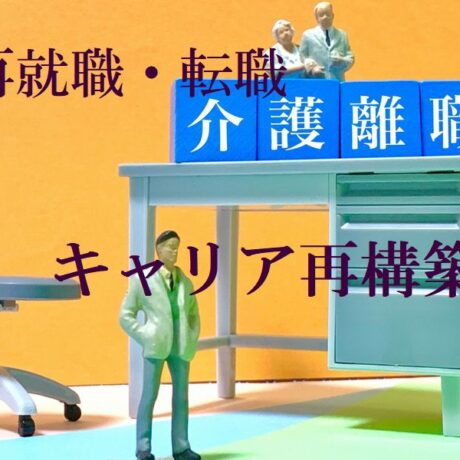

コメント