3. 子どもが受けるチャイルド・ペナルティ
チャイルド・ペナルティが真に深刻なのは、それが親の世代だけの問題で終わらず、子どもたちの機会と未来を奪う連鎖を引き起こすことにあります。
親が経済的・時間的な制約を受けることで、子どもは「所得の貧困」と「時間の貧困」という二重のペナルティを負い、その影響は彼らの成長過程全体に及びます。
そこで受けるペナルティの種類を整理しました。
1)親の所得・時間・地域による教育格差の発生
親の経済的・時間的ペナルティは、子どもの教育における機会格差を拡大させます。
これは、以下のように、親の所得、利用可能な時間、そして居住地域という三つの要素が複雑に絡み合い、子どもの学習環境・学習条件を決定してしまう問題です。
・所得による格差:親の低賃金・賃金低下は、塾や習い事、参考書などの教育投資の機会を奪います。
・時間による格差:親が長時間労働や不安定な非正規雇用で忙殺されることで、子どもと向き合い、対話したり学習をサポートしたりする「時間的資源」が不足します。
・地域による格差:地域間の財政力や教育資源の偏り、質の高い公的保育・教育機関へのアクセス格差も、ペナルティを深刻化させます。
2)経済的困窮と親の疲弊によるいじめ・不登校リスク化
親が抱える経済的・精神的な不安や負担、DV(ドメスティック・バイオレンス)などは、家庭内と子ども自身のストレスとなり、子どもの心身の健康や学校生活にも影響を及ぼします。
以下のような問題は、教育現場も認識あるい注意が必要な課題としても指摘されてはいます。
・経済的困窮と社会的排除:貧困状態にある家庭・家族の子どもは、友人との活動や服装などで経済的な差を感じやすく、これがいじめや自己肯定感の低下につながることがあります。
・親の心理的資源の枯渇:親が仕事やケアで疲弊し、子どもの悩みに寄り添う時間や気持ちの余裕を失うと、子どもは孤立し、不登校のリスクが高まります。
・学校の脆弱化:教員の長時間労働や多忙化も進む中、経済的に困難な家庭の生徒や、複雑な事情を抱える生徒へのきめ細やかなサポート体制が未整備あるいは欠落・脆弱化しています。
3)子どもの機会を奪う貧困の世代間連鎖
チャイルド・ペナルティの最大の脅威は、このペナルティが子どもの成長を通じて再生産され「貧困の世代間連鎖」を引き起こすことです。
つまり、このペナルティは、親の責任にとどまることなく、社会の構造が次の世代に貧困を継承させてしまう問題なのです。
・機会の不平等:十分な教育や経験機会を得られなかった子どもは、成人後に低賃金・不安定な職に就く可能性が高まります。
・自己肯定感の低下:貧困の中で育つことで、自分には能力がない、努力しても無駄だと感じる「学習性無力感」を抱きやすく、将来に向けた意欲や挑戦意欲が減退してしまいます。
4)子どもに重荷を課すヤングケアラー問題
ヤングケアラー問題は、本来大人が担うべきケア責任を子どもが負う状態を指します。
ヤングケアラーの発生要因は多様かつ複合的です。
しかし、その多くは、親自身の病気・障害・精神疾患あるいは 不就労などによる 「大人のケア責任の欠如・限界」 に起因します。
親の チャイルド・ペナルティ(特に長時間労働やキャリア断絶) もその一因となりますが、問題の核心は、 ケア体制の公的な不備と社会的孤立にあることを確認しておくべきでしょう。
本質的に、根源的に、以下のような状況を招きます。
・家族のケア役割の代行:親の病気、障害、あるいは弟妹の世話など、子どもが重すぎるケア責任を負うことになります。
・学業・進路への影響:ケアに時間を取られるため、宿題や受験勉強の時間が確保できず、学業成績や進路に深刻な影響が生じます。
・子どもの権利の侵害:子どもの成長にとって必要な遊びや休息、教育を受ける権利が奪われており、これは「子どもの社会的権利」の重大な侵害です。
5)ペナルティ極大化:障害児家庭と支援の地域格差
障害を持つ子どもを育てる家庭は、一般的な子育て家庭よりもさらに大きな以下のようなペナルティに直面し、その負担は公的支援の地域差によっても増幅されます。
そしてその大半は、女性が担っており、ジェンダー規範と通じるところです。
・母親のキャリア断絶:重いケアが必要となるため、母親が仕事を辞めざるを得ないケースが多く、チャイルド・ペナルティが極大化します。
・支援サービスの地域格差:障害児支援サービス(医療的ケア児支援、放課後等デイサービスなど)の質や量に地域間で大きな差があり、支援が不足する地域では、親の負担が限界を超えやすくなります。
6)ペナルティ連鎖を断ち切る:子どもへの直接支援と残された課題
子どもが受けるペナルティの連鎖を断ち切るには、親への支援と並行して、子ども自身に直接「機会」を提供する社会的・公的支援が必要です。
子ども自身が受けるチャイルド・ペナルティという視点や課題は、現状、社会的・政治的に強く認識されているとは言えません。
以下の対策なども、貧困対策として位置付けられることがあっても、ヤングケアラー対策として取り扱うことは極めて稀なことと考えます。
・包括的な教育支援:学校外での学習機会を保障するための公的な塾や居場所づくり、教育バウチャー制度などが求められます。
・給付型奨学金の拡充:家庭の経済状況に関わらず、意欲ある若者が高等教育へ進学できるよう、返済不要の奨学金制度を大幅に拡充する必要があります。
・ヤングケアラー支援の法制化:子どもが担うべきでないケア責任を社会が引き受けるための、相談窓口の整備、アウトリーチ、福祉サービスへの確実なつなぎ込みが急務です。



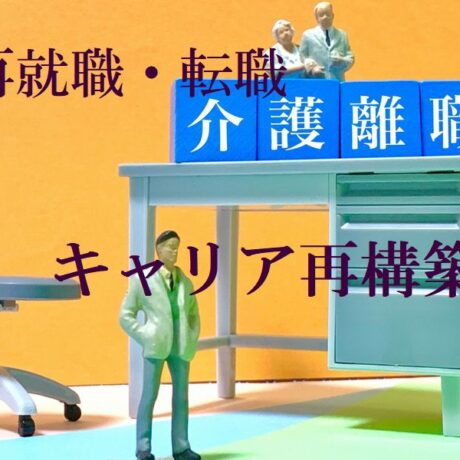

コメント