介護支援格差が一層の介護格差を招く|介護離職格差の拡大へ
はじめに|「東京海上、介護離職防止のための一時金20万円支給」日経記事から
10月19日付日経に、以下の記事が掲載されました。
⇒ 介護離職防止へ一時金 東京海上日動が20万円 – 日本経済新聞
以下にその記事を要約します。
東京海上日動火災保険は、介護が必要な親族を持つ社員に対し、ケアサービスなどの費用として一時金20万円を支給する新制度を導入する。
これは、企業が介護費用を現金で支給する珍しい取り組みです。
1)背景:増える「仕事と介護の両立」問題
目的は、社員が早期に介護支援を利用し、仕事と介護の両立をしやすくすることで離職を防ぐことです。
管理職層を中心に、介護と仕事の両立に直面する中高年社員が増加。
経済産業省は2030年までに約318万人が両立し、年間約9兆円の経済損失が発生する可能性があると試算しています。
また、厚生労働省は改正「育児・介護休業法」により、企業に介護支援のための研修・相談体制の整備を義務化(2024年4月~)しました。
2)東京海上日動の支援内容と対象
・対象: 「要介護1」以上の親族を持つ社員(社員の約1割が直面という社内調査結果に基づく)。
・支給額: 20万円(要介護1の介護サービス自己負担額に基づき設定)。
・目的: 要介護1のような介護の初期段階にある社員に、認定取得やサービス利用を促し、後の離職リスクが高まるのを防ぐ「早期支援」を意図しています。
・介護休暇制度の拡充
新たに年5日間の介護休暇を新設し、既存の制度と合わせて最大15日間・1時間単位で取得可能とするなど、柔軟な勤務体制を整備しました。
3)他の金融機関でも広がる介護支援制度
・山口フィナンシャルグループ(FG)の最長3年間(93日間有給)の介護休暇制度
・第一生命ホールディングス(HD)の業務代行同僚への手当支給(最大95万円)
・明治安田生命保険の週休3日制選択導入
など、金融業界全体で独自の介護支援が加速しています。
企業による「介護と仕事の両立支援」が加速
少子高齢化が進む中、企業が社員の介護負担を軽減し、離職を防ぐための具体的支援策を導入する動きが加速しています。
同社のような一時金制度や業務代行手当は、介護問題を「個人の責任」から「組織全体の課題」へと位置づけ直す新たな流れの象徴といえます。
介護格差の一層の拡大を招く介護支援格差
しかし、こうした大手企業の独自の介護支援制度導入の例が取りあげられるたびに想起することがあります。
それは、企業間を初めとする介護支援制度内容の格差と総合的な介護支援制度の利用度自体の格差がますます拡大し、結果として総体としての介護格差の拡大にも繋がっていくということです。
今回はその問題について、同記事の内容を参考に、介護支援格差と介護離職格差の動向などについて考えてみたいと思います。

1.介護支援制度とは|死角としての介護支援格差
「介護支援制度」とは、従業員が家族の介護を理由に離職することなく、仕事と両立できるようにするために設けられた仕組みの総称です。
この制度は、主に「法律で義務付けられた制度」「企業が独自に導入する制度」「自治体独自の制度」の3つに分類できますが、それぞれの運営・利用実態に大きな格差(介護支援格差)が存在します。
以下、それらについて整理してみました。
1-1 法律で雇用主に義務付けた介護支援制度「育児・介護休業法」と介護支援格差
介護離職防止対策の根幹は「育児・介護休業法」であり、2025年4月~段階的に施行される改正では、介護離職防止・仕事と介護の両立支援制度の強化が盛り込まれています。
1)介護休業制度:
要介護状態にある家族を介護するために、対象家族1人につき通算93日まで(3回まで分割可能)休業できる制度です。
法律上の最低限の保障ですが、休業中の賃金は原則無給であるため、雇用保険から支給される介護休業給付金(休業開始時賃金の67%)の活用が前提となります。
2)介護休暇制度:
要介護状態の家族の世話や病院の付き添いなど、突発的な用務に対応するために、年5日間(対象家族が2人以上の場合は年10日間)を1時間単位で取得できる制度です。
3)介護支援体制づくり:
2024年・2025年からの改正により、企業には以下の措置を講じることが義務化されました。
・個別周知・意向確認: 従業員から介護の申出があった際、制度の内容を個別に伝え、利用意向を確認すること。
・早期の情報提供: 従業員が介護に直面する前の早い段階(40歳時など)で、介護支援制度に関する情報を提供すること。
・雇用環境の整備: 研修の実施、相談窓口の設置、事例の収集・提供など、制度利用を促進するための環境整備措置を講じること。
企業制度整備の実態調査でも、6割以上の企業が改正対応を進めていますが、その内容は制度・規程の見直しや就業規則改定など、形式的な整備が中心という報告もあります。
4)「育児・介護休業法」の利用状況が示す介護支援格差
これらの制度は法律上の義務ですが、その利用率は依然として低い水準にとどまっています。
その背景には、「制度はあっても利用しにくい」「上司や同僚に迷惑がかかる」「キャリア形成に影響が出る」といった職場文化や心理的要因が深く関わっています。
また、企業規模の違いにより、当然、こうした法律の遵守・実行が困難という問題があることも想像できます。(次項で詳述)
これは、「形式的な制度の存在」と「実質的な利用可能性」の間に生じる格差であり、法制度が定める枠内での「介護支援格差」といえます。
1-2 企業等民間事業者が独自に導入する介護支援制度と介護支援格差
1)企業等独自の介護支援制度導入例|介護離職を防ぐための企業の取り組み状況
ここ数年で、大手企業を中心に「介護離職防止」への制度強化が広がっています。
・冒頭の日経記事における事例:
東京海上日動の20万円の一時金、第一生命HDの業務代行者への手当、山口FGの最長3年間(93日超無給)の介護休業、明治安田生命の週休3日制など、法定水準を大きく上回る手厚い支援策が導入されています。
・その他の事例: 介護費用の補助、ベビーシッターならぬ「介護シッター」費用の補助、外部専門家による無料相談サービスの提供などが挙げられます。
ただし、職場における「介護支援体制が整っている」と回答した企業は少なく、支援制度周知・利活用促進・相談窓口の設置などの課題が残っています。
例えば、ある調査では「支援体制が整っている」と感じる従業員は3割程度という報告もあります。
また、大企業と中小零細企業等企業規模格差や、業種の違いが介護支援制度格差に直結していることも、頻繁に取り上げられています。
2)企業内利用度による介護支援格差
大手企業の手厚い独自制度であっても、企業内部で格差が生じます。
高業績者、管理職、中核事業部門の社員など、代替要員確保が難しいポジションにある従業員ほど、手厚い制度があっても利用をためらいがちです。
また同一企業であっても上司や組織風土などにより制度活用度に違いがありえますね。
制度の利用しやすさが職務や評価に依存することで、「企業内利用度」という形で介護支援格差が生まれているのです。
3)企業間格差による介護支援格差
これは最も深刻な格差です。
大企業や資金力のある金融機関が手厚い独自制度を導入する一方で、中小企業の多くは、法定の制度(育児・介護休業法)すら十分に整備できていません。
中小企業では「人員が少なく代替要員が確保できない」「人事・労務担当者が不足し制度整備が進まない」といった構造的な課題があり、この「企業規模」そして想定されることではありますが「経営状態・財務状態」による従業員支援格差が、介護離職格差に直結しています。
企業独自の介護支援制度を制定する余裕など論外、ということにもなります。
1-3 自治体が独自に制定し、運営する介護支援制度と介護支援格差
1)自治体独自の介護支援制度導入例
地方自治体は、国の介護保険制度を補完する形で、地域の実情に応じた独自の介護支援サービスを提供しています。
以下にその例を挙げました。
・在宅介護支援サービス: 介護保険ではカバーできない家事支援や見守りサービスへの費用補助、緊急時対応のための独自の短期入所(ショートステイ)枠の確保など。
・介護者支援: 家族介護者向けのレスパイトケア(休息)のための補助金、認知症サポーター養成講座の実施、介護に関する地域情報提供サービスの充実など。
2)自治体ごとの介護支援への取り組みにおける介護支援格差
自治体による支援は、その地域の「財政力」や「高齢化率」、そして「行政の介護施策への注力度」に大きく依存します。
・都市部と地方の格差: 財政力の豊かな自治体は、介護保険の自己負担軽減策や、きめ細やかな独自サービスを上乗せして提供できます。
一方、財政の厳しい自治体では、法定水準のサービス提供で手一杯となり、独自の支援がほとんど行えない場合があります。
・サービス提供体制の格差: 過疎地域では、介護人材や施設自体の不足が深刻化し、自治体が独自に支援策を打ち出しても、実際にサービスを提供する事業所がないという「サービス供給格差」に直面します。
介護支援制度を3つの管理運営主体それぞれの視点から見てきました。
しかし、それぞれの枠内において、その制度を利用できる人、できない人の格差が厳然としてあることが分かりました。
これは、介護格差の一要素・要因と考えてよいと思います。
そこで、包摂的な「介護格差」について、次に確認することにします。
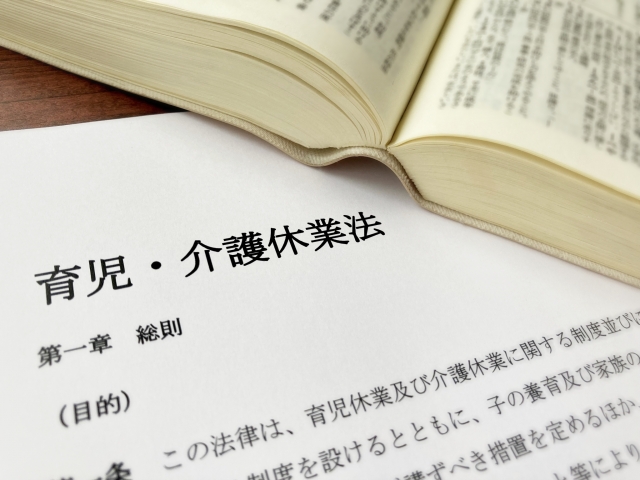
2.介護格差とは
「介護格差」(かいごかくさ)とは、誰もが等しく必要な介護サービスを受けられるとは限らず、住んでいる地域や経済力、家族・人間関係の状況などによって、受けられる介護の質や量に大きな差が生じる社会問題のことです。
2-1 介護格差の主な要因と具体的な内容
介護格差は主に以下の5つの側面で発生しています。
1)経済的格差(所得・資産による格差)
経済力は、受けられる介護サービスを大きく左右します。
・自己負担の差:
所得が低い世帯では、介護保険サービスの自己負担額(原則1割、所得に応じて2〜3割)を支払うために必要なサービス利用を控えるケースがあります。
富裕層は高額な有料老人ホームや介護保険外の自費サービスを自由に利用できます。
・介護離職のリスク:
経済的に余裕がない場合、家族が仕事を辞めて介護せざるを得ない介護離職につながりやすく、さらに世帯収入が減るという負の連鎖を引き起こします。
2)地域格差(居住地による格差)
住んでいる地域によって、利用できる介護サービスの種類や量、保険料の額に差が生じます。
・サービス供給量の差:
都市部では施設不足による「介護難民」が、過疎地域ではサービスを提供する事業所自体がない「介護限界地域」が生じています。
・介護保険料の差:
介護保険料は市町村ごとの高齢化率やサービス給付費によって決まるため、地域によって差があり、全国平均を大きく上回る地域もあります。
3)人間関係・情報格差
家族構成、人間関係、情報収集能力も介護の明暗を分けます。
・人的資源の差: 身元保証人や緊急時の対応を担う家族・親族の有無が、施設入居の可否や介護の継続性に大きく影響します。特に「おひとりさま」高齢者にとって深刻です。
・情報格差: 介護サービスや公的な制度について知っているか否か(情報格差)が、受けられる支援の質に決定的な差を生みます。
4)性別・家族構成の格差
・女性への負担偏重:
伝統的に女性に介護負担が偏りやすく、「老老介護」や「単老介護」が増加しています。
・介護者の確保困難:
子どものいない世帯や独身高齢者では、介護者の確保そのものが困難です。
5)介護サービス資源・専門職の格差
・人材の質と量の格差:
介護人材の不足と低賃金の問題により、介護職員の質の維持や確保が難しく、ケアマネジャーやヘルパーの質・経験・人数に地域差が生じます。
・サービス提供事業者間の質の差: 結果的に提供されるサービスの質にも地域や事業所による差が生じ、利用者の選択肢が限定されます。
2-2 介護格差がもたらす社会的影響
介護格差は、単に高齢者自身の問題にとどまらず、社会全体に影響を及ぼします。
その例を挙げました。
1)格差の拡大と固定化:
貧困や孤立が、さらに介護の困難さを生むという負のサイクルを生み出します。
2)現役世代への負担増:
サービスが不足することで、現役世代が「仕事と介護の両立」(ダブルケア含む)を強いられ、介護離職や貧困のリスクが高まります。
3)社会の分断:
誰もが等しく安心できる老後を送れないという不安が社会全体の将来不安を増大させます。
4)社会保障制度への不信感と分断の拡大:
介護保険料を支払っていても十分なサービスが受けられない地域や層が増えることで、制度の公平性・持続可能性に対する不信感が高まり、国民間の対立を招きます。
5)介護を受ける人の生活の質(QOL)の格差拡大:
経済力や居住地域によって、受けられるサービスの量や質に差が生まれるため、高齢者自身の尊厳や健康維持の度合いに大きな不均衡が生じます。
6)介護者の経済的・精神的な疲弊や離職の増加:
公的支援や企業支援の格差により、一部の家族に負担が集中し、共倒れのリスクや「老老介護」の深刻化、そして介護離職へと直結します。
7)地域間の人口流出・高齢化の偏りの加速:
介護サービスが不足している地域や、費用負担が大きい地域から、現役世代や若者が流出し、その地域の高齢化が一層進むという悪循環を招きます。
2-3 政策的課題と今後の方向
介護格差を是正するためには、次のような対策が求められます。
1)地域包括ケアシステムの充実:
地域差をなくすため、医療・介護・福祉を一体的に提供する仕組みの整備を進め、住み慣れた地域で必要なサービスを受けられる体制を強化します。
2)所得に応じた介護費負担の再設計:
低所得層への補助や給付付き税額控除の活用などにより、経済的な理由で必要な介護を諦めることのないよう、公平な負担構造に見直します。
3)介護人材の処遇改善と均衡配置:
介護職員の給与水準を引き上げ、専門職の地方への配置を支援することで、介護サービスの質と量の地域格差を是正します。
4)家族介護者支援制度の強化:
企業における介護休業・短時間勤務制度の柔軟化や、専門的な相談支援体制の拡充を通じて、現役世代が仕事と介護を両立できるようサポートします。
5)ICT・AIによる介護支援の普及:
見守りシステムや介護記録アプリなど、テクノロジーの導入を支援し、在宅介護における家族の身体的・精神的な負担を軽減します。
以上、介護格差について概括しました。
「介護格差」とは、単なる経済的な差ではなく、社会構造全体が生み出す生活機会・福祉サービス・家族支援の不均衡を映し出す概念です。
真に「シン安保2050」における生活や社会保障の安心・安全・安定を基盤とした「シン日本社会2050」の実現を目指すためには、介護格差の是正は避けて通れない重要個別課題の一つといえます。

3.介護離職の実態とその要因としての介護支援格差・介護格差
3-1 介護離職の最近の動向
1)年間の介護離職者数
・厚生労働省「雇用動向調査」によれば、2023年(令和5年)における「介護・看護」を理由とする離職者数は約7.3万人(男性約1.7万人、女性約5.6万人)となっており、女性が約77%を占めています。
・また、総務省「令和4年就業構造基本調査」では、直近1年間に「介護・看護のため」に前職を離職した人は約10.6万人となっています。
・過去10年間で大きな減少はなく、高止まり傾向が続いています。
2)介護離職者の主な属性と傾向
・性別:
女性の割合が高いが、近年は男性の割合も上昇傾向にあり、特に50代の管理職層の増加が顕著です。
これは、共働き世帯の増加や、男性が介護の担い手となるケースが増えている現状を反映しています。
・年代:
40~60代が中心で、特に40代後半~50代後半が全体の約6割を占めます。
親の介護と自らのキャリア・子どもの教育費などが重なる「トリプルケア層」が課題化しています。
・離職までの期間:
介護を始めてから仕事を辞めるまでの期間は、「6か月未満」と回答する人が半数以上を占めた調査結果もあり、事前の準備期間がないまま短期離職を余儀なくされるケースが多いことを示唆しています。
・雇用形態: 離職者の約8割が正社員・契約社員であり、パートタイム層にも増加傾向がみられます。
3-2 介護離職の主な理由と背景にある意識
1)離職の真の理由:望まない離職が多数
離職に至る主な理由としては、「勤務先の両立支援制度が十分に整っていない」「介護休業等を取得しづらい雰囲気」「介護サービス・介護保険制度を十分に知らなかった/利用できなかった」という点が挙げられています。
| 主な理由内容 | 具体的な背景 |
| 介護体制の限界 | 介護サービスの空きがない、利用調整が難しい、在宅負担が大きい |
| 職場環境の制約 | 時間の融通がきかず、在宅勤務・短時間勤務の利用が難しい |
| 心理的・身体的負担 | 介護の長期化・孤立・ストレスによる疲弊 |
| 経済的理由 | 介護と勤務の両立で収入減・昇進停滞、結果的に退職を選択 |
特に「制度があっても使いづらい」「上司・同僚に理解されにくい」といった職場文化の問題が離職要因として浮上しているのが特徴です。
2)介護離職の背景にある意識
介護離職を経験した人の約85%が、「本当は働き続けたかったのに、望まない形で離職せざるを得なかった」と回答しています。
また、「介護は自分がやらなければならない」という強い意識を持っている人ほど、制度の有無にかかわらず離職しやすいという調査結果も報告されており、介護の社会化に対する意識改革も課題です。
3-3 企業への影響と経済損失|社会的・企業的インパクト
1)労働損失とコスト
・経済産業省の試算では、2030年には介護と仕事の両立者が約318万人に達し、それに伴う労働損失は約9兆円規模に上ると見込まれています。
・企業側では、離職後の人材補充コスト・再雇用コスト・生産性低下を含めると、企業1社あたり年間数百万円〜数千万円規模の損失が生じるとされます。
・企業側では、介護離職を防ぐための勤務制度や支援体制の整備が、人的資本経営や人材定着の観点から重要視されています。
3-4 今後の課題と展望
1)主な課題:
・制度の形骸化: 制度は整いつつあるものの、実際の利用・活用が十分でない(例えば、介護休業取得率が非常に低い)。
・企業・事業所による支援の格差:
地域・業種・企業規模による格差が大きく、特に中小企業(約6割で介護相談窓口が未整備)での制度整備の遅れが深刻。
・介護サービスの地域格差:
地方・過疎地域で介護施設や訪問介護事業者の不足が深刻。
・男性介護者への支援拡充:
男性は「職場で相談しにくい」「制度を知らない」など情報不足が目立つ。
2)今後の展望:
・高齢化の進展とともに、介護をしながら働く人(「ビジネスケアラー」)の増加が見込まれており、特に団塊の世代が全員後期高齢者となる2025年以降がひとつの節目(「2025年問題」)として注目されています。
・企業は単に制度を設定するだけでなく、「実際に使いやすい支援環境」「職場文化としての理解」「介護と仕事の両立を可能にする働き方の柔軟化」を整えることが重要です。
労働市場・企業経営の観点からも、優秀な人材の定着や働き続けられる環境づくりが経営課題化しており、今後支援制度の活用促進や企業の実践事例の共有が進む可能性があります。
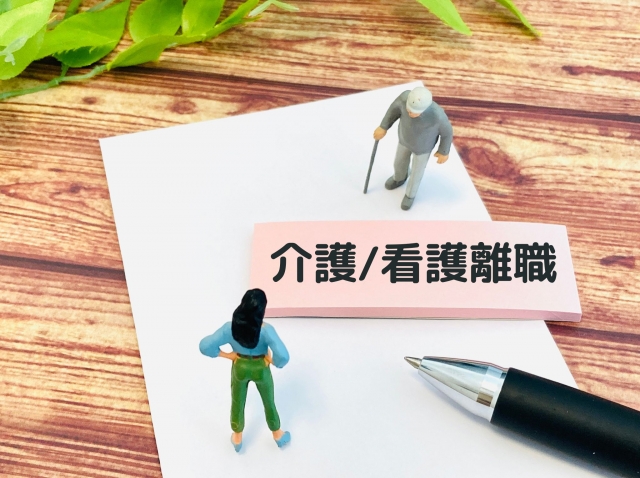
まとめ|介護離職抑止の根本的な施策は?
介護離職は、依然として年間数万人規模の社会的損失を生む深刻な課題であり、40〜50代の働き盛り世代、女性が特に影響を受けやすいという特徴があります。
制度整備が進む一方で、実務上の活用・職場の雰囲気・支援体制において課題が残っています。
介護離職実態が示す介護離職格差
介護離職は、誰もが等しく直面するリスクではありません。
介護離職者と両立継続者との間には、勤務先の規模、職場の文化、居住地域のサービス供給量など、さまざまな要因に基づく「介護離職格差」が厳然として存在します。
介護支援格差も介護離職格差の要因に
本記事で見てきたように、「法律」「企業」「自治体」という3つの運営主体すべてにおいて、支援制度の「存在」「内容」「利用しやすさ」に大きな格差(介護支援格差)があります。
・大手企業の独自支援(東京海上日動の一時金など)は、社員にとっては大きな安心材料ですが、その手厚さゆえに、それが享受できない中小企業社員との間に強烈な格差を生み出し、格差の再生産を招いています。
・法制度は最低限のラインですが、職場の文化という壁に阻まれ、「利用できる人/できない人」の格差を生んでいます。
・自治体支援は、地域の財政力という壁に阻まれ、「地域格差」を固定化しています。
多様な介護格差が、介護離職格差拡大要因に
経済力、地域、情報、家族構成といった複合的な「介護格差」が、先に述べた「介護支援格差」と結びつくことで、介護離職に至るか否かの「介護離職格差」が拡大・固定化しています。
貧困層や中小企業社員、サービス不足地域に住む人は、支援が手薄な中で介護を強いられ、離職リスクがより高くなるという負のサイクルです。
介護離職を根本的に抑止することは可能か
介護離職を根本的に抑止するためには、単に「休業制度」を設けるだけでなく、介護の負担自体を個人・家族から社会全体へ移行させる「介護の社会化」をさらに徹底することが鍵となります。
すなわち、公的介護保険制度の改善・改革が不可欠と考えます。
具体的には、以下の格差是正に向けた施策が不可欠です。
・企業間格差の是正: 中小企業に対し、代替人材確保のための補助金や、専門家による介護支援コンサルティングを強化し、法定制度を「使える」ものにする。
・制度の利用促進: 法的義務にとどまらず、マネージャー層への徹底した研修や、業務の属人化解消(チーム内での業務代行を容易にする仕組み)を通じて、制度利用を歓迎する職場文化に変革する。
・地域格差の解消: 財政力の弱い自治体へのサービス供給支援を強化し、介護サービスへのアクセス(供給量・質)を均等化する。
政府による法的支援義務化を契機に、企業・自治体・介護事業者が一体となった「介護と仕事の両立支援社会」の構築が今後の焦点であり、格差の拡大を放置せず、包摂的な支援体制を目指すことが急務です。
自分のこととしての介護離職リスク、介護離職格差、介護支援格差に備える|介護格差の自己化再考
ここまでは、一般論としての介護格差、介護支援格差、介護離職格差について整理しました。
しかし、現実には、個々の介護する人、介護される人の関係性や、経済力、住まいの状況、仕事の事情そして地域の事情は皆異なります。
まったく同じ事情・状況は皆無であり、大半を社会が対応すべき課題としていることで、その対応が適切に行うことができるとは限りません。
いや、そうした「社会」と「社会化」の対応・対策を待っていては、恐らく、介護離職格差が縮減され、介護離職自体が明確に減少することはないと思います。
絶対に介護離職しない介護対策
ここで申し上げておきたいのは、「絶対に介護離職せずに介護を担う方策をとことん考え、準備しておくこと」です。
「社会化」を待つがけではなく、「自己化」を決意し、介護離職しないで取りうる対策はどういうものか、すぐにでも調査と検討を始めましょう。
介護格差が一朝一夕で改められるはずもありません。
介護支援格差を埋めることも、自助努力では限界があります。(自治体の支援制度は調べつくしましょう。)
しかし、介護離職格差・介護離職リスクは、基本的には、自身が動かなければ何も変わりませんが、自助努力・自己化で、自ら埋めることは可能です。
・要介護3以上は、特養入所を
とりわけ、要介護3以上の家族の介護においては、特養への入所を目指すべきです。
その壁となるのが、自宅介護を希望する親や夫や妻。介護を受ける家族が、特養への入所を受け入れるような、事前のコミュニケーションを常日頃から行い、地ならししておくことをお薦めします。
その場合でも、やはり絶対条件になるのが費用。
これは、介護を受ける家族の預貯金や年金収入をまず充当しますが、不足する場合は、介護する方の給与など、介護離職せず働き続けることで得る所得の一部を補填することもやむを得ないと考えます。
なお、介護する人・される人の住まいが離れている場合、特養入所時の後見をしてくれる近くに住む人をなんとか手配します。どうしてもいない場合は、介護する人の住まいの近くの特養を手配し、何とか引っ越してくれるよう説得しましょう。
「介護・子育て支援法」で規定された介護休業や介護休暇は、特養探しや入居申し込み・諸手続きに利用します。
親や夫婦どちらかが絶対自宅で、と固執する場合、果たして自分ならばどうするか、どうすれば介護する人が助かるかをとことん考え、自分なら入所を選択する心境・心持になる必要があります。
・要介護2以下の介護の場合|介護制度・介護保険制度を熟知し、最善の方法で対処する
上記外の要介護・要支援状況の場合は、とにかく介護制度・介護保険制度を調べつくし、自分と介護すべき家族の種々の状況・条件と擦り合わせて、ベターの選択を見つけ出します。
なんとか休みや介護支援法を活用しながらの「仕事と介護の両立」になるため、通所介護や訪問介護などをそれらに合わせて、組み合わせ、利用することになります。
これも、介護を受ける家族の身体的・心理的状況により、個々にまったく対応方法がことなるため、学習と情報収集が必須です。
また、ケアマネージャーにとどまらず、信頼できる相談相手も確保したいですね。

なお、現状、介護終活.comというサイトで、「介護離職」対策のためのシリーズ記事を公開しています。
いずれ、その内容は、当サイトに移行する予定ですが、それまでは、見て頂けますので、多少なりとも参考になればと思います。
⇒ 【入門編】介護離職の定義と現状を知る!「介護離職しないための8ステップ+1」スタート – 介護終活.com
⇒ 【シリーズ総括】「介護離職ゼロ」は実現できる?「介活」で考えるこれからの介護 – 介護終活.com
ーーーーー
介護離職は、依然として年間約9万人規模の社会的損失を生む深刻な課題であり、日本の少子高齢化・働き方の変化の中で、重要な社会・労働政策課題となっています。
特に働き盛り世代の離職が企業・経済双方に大きな影響を与えている。
最新のデータでは年間で数万人規模の離職が発生しており、特に40〜50代の働き盛り世代、女性が影響を受けやすいという特徴があります。
制度整備が進む一方で、実務上の活用・職場の雰囲気・支援体制において課題が残っており、今後は「使える制度」と「継続できる働き方」を両立させることが鍵となるでしょう。
企業・政策・個人の三者が協働して、介護離職を防ぎ、働きながらの介護支援を可能にする環境づくりが急務です。
政府による法的支援義務化を契機に、
企業・自治体・介護事業者が一体となった「介護と仕事の両立支援社会」の構築が今後の焦点である。




コメント